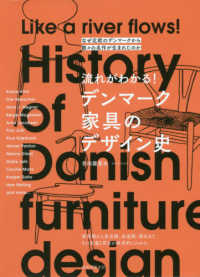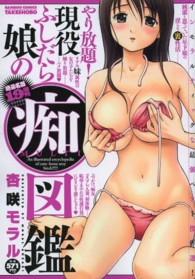内容説明
太古、豊かな照葉樹林に囲まれていた日本列島。しかし二千年前の登呂遺跡から出土した木製品はスギ材にかわり、現在の白砂青松はさらなる森の荒廃を証明している。日本の環境破壊は弥生時代に起こっていた―。「森の文化」と呼ばれるわが国で、人びとは森林とどのように接してきたのか。そしてその先に見えてくる、文明と自然の共生関係とは何か。
目次
序章 森・林・木・人
第2章 森の文化史
第3章 気候を表現する
第4章 移りゆく自然
第5章 森のエコシステム
第6章 森の環境学
終章 いつまでも森の恵みを得るために
著者等紹介
只木良也[タダキヨシヤ]
1933年生まれ。京都大学大学院農学研究科林学専攻修了(農学博士)。農林省林業試験場勤務、信州大学理学部教授、名古屋大学農学部教授を経て、現在はプレック研究所生態研究センターセンター長。専攻は造林学、森林生態学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テッテレこだち
0
森の分類とか育ち方の違いとかがわかりやすい。でも最終章も含めて、もともとが昭和に出版された本だとは…。大学で似たような主張を、つい一昨年聞いたばかりだ…。2012/01/31
徳島の迷人
0
原本は1981年だが、数字は最新(2004年)のものに変えられている。文化史というより理系的な「森林学概説」。数字は多く、各植生が詳しい。我が母校・学部の教授経験者が書いているからか内容はほとんど既に知っていたが、地上高・地下深さ毎の森林の乾重は知らなかったのでためになった。原本は1980年代~2000年代は林業低迷期に入っていたので、産業としては少し暗め、補助金等で公益的機能を発揮させるのもやむなし、といった雰囲気で論が進む。森林学を知りたい人にはオススメ。興味を持ったら毎年発行される林業白書も読もう。2022/07/13
Sunny
0
保全の意義を遷移と共に述べられていて納得。 砂浜は上流の環境破壊の証拠というのは目から鱗。 15年以上前の本なのでUpdateが要りそうな内容。里山って今まだあるんでしょうか。2020/03/25
_mOtOm_
0
花崗岩 こならアカマツ 生き残る 回復すると マツタケ高騰2019/04/09