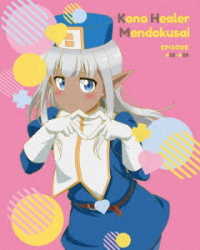内容説明
聖なる秘仏は呪力を持つとされ、人びとはこの力の現世利益を求めて集まる。著者は、このような仏教と呪力信仰との関係を理解するためのヒントを民俗信仰のなかに見る。たとえば、わが国の民俗レベルの呪力信仰の中心に活躍するシャーマンたちとその宗教施設は、東北や南西諸島に限らず、むしろ東京などの大都市圏に多く存在するという。聖と呪力をめぐる問題を宗教人類学的に考察した期待の力作。
目次
1 霊魂と民俗信仰(民俗信仰とアニミズム文化;「死」の民俗;「葬祭=仏教」と霊魂観)
2 民俗宗教の諸相(沖縄・久高島のイザイホー;「カゼ」と「インネン」―長崎県・福江島の宗教文化;都市シャーマニズムの考現学 ほか)
3 聖と呪力(僧の呪師化と王の祭司化;巫的文化の諸相―『宇治拾遺物語』の考察;憑入・憑着・憑感―憑霊の概念 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
56
仏法を護る護法童子が、験者に操られて病魔悪霊を退散させるのは奇妙なことである。《聖と呪力》の一体化した日本型信仰はどこから来たのだろう。それは中心に座す神仏と周縁で飛遊するカミという基本構造からなり、全体を大きく支えるのはカミに自己委譲する「霊媒」と、中心の神仏の力を借りてカミを操る「予言者」と、神仏を外から祀る「祭司」の三者関係だ。著者はさらにホカートの王権論を援用して巫王から祭司王への変貌を説く。なるほど失われた王の呪力を補うために、加持僧や陰陽師が護法童子や式神を操り始めたというのはわかる気がする。2017/11/20
Mark.jr
5
オカルティックなところもありますが、基本はレヴィ=ストロースの構造主義的人類・民俗学の延長線にあるキッチリとした内容です。しかし、堅苦しいだけではなく、創作にも役立つのではないかという、取っつき安さもあります。2024/08/12
ゲニウスロキ皇子
5
五島列島の福江において病める人々が、近代の象徴たる病院と伝統的な呪術医のもとを行き来している様は面白い。また、メガロポリスの暗部には、この世ならざるものがリアリティを帯びているということを改めて思い知らされた。多様な宗教的背景を持つ人が集う都市は、まさしく宗教経験の坩堝であるといえるだろう。このような記述を新鮮な気持ちで読めるということは、まだ自分は近代と伝統という厳然たる思考の枠組みに囚われているんだろうなあ。2011/11/17
Jagrass03
5
この世ならざる力を獲得するには全てを投げ出す覚悟が必要なんだなと思った。沖縄のカミダーリィの事例と、修行型宗教者と召命型宗教者の違いで、後者は覚醒前に修行のような人生苦を味わっている場合が多いという指摘が興味深かった。2011/07/05
さんとのれ
3
古代シャーマンに束ねられていた国は、安定した社会をめざし祭司化した王をいただくようになる。不安定要素であるシャーマンは遠ざけられるが、日本においてはその隙間を仏教が埋めたと考えられ、仏教とシャーマニズムは長く併存していく。思い通りにならない、理解不能な現実への説明として今でも必要とされているシャーマンは興味深い存在だけど、組織化すると途端に胡散臭くなるのはなぜ?2015/02/04
-

- 電子書籍
- 蒼い世界の中心で 第05話【単話版】 …
-

- 洋書
- NATURE