内容説明
バルト、ラカン、デリダ、ボードリヤールなどのフランスの思想家を中心に、構造主義から記号論への展開を考察。また、二十世紀の消費社会がもたらした映画、写真、デザインなどの大衆文化をも記号論の視点で解読する。著者は様々な記号と思考がからみ合う生態学的な状況において、記号論を形式的な分析装置にはとどめない。現代思想全体への鋭い批評精神を持つ記号論の豊かな可能性を説く意欲作。
目次
1 記号論の哲学
2 模倣と引用の世界
3 思想のカオスモス
4 記号論の現在
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
karatte
16
再読。丁度ドゥルーズの『差異と反復』を読んでいて、シミュラクルについて書かれた本を手当たり次第に探していた頃、今は亡きららぽーと志木店の新星堂で見つけて買ったもの。さほど思想的な影響は受けていないが、現在もご存命とのことなので、是非昨今のケータイ・スマホのデザインについて意見を伺ってみたいものだ。2017/09/18
またの名
7
「意味スルモノ/サレルモノ」という翻訳語を頑固に貫いたフレンチセオリーの先導者の小論集。フロイト、ラカン、ドゥルーズ=ガタリ、ベンヤミン、ボードリヤール、モラン、ニーチェ、デリダ、バシュラール、サルトル、ジラールらの名前が消費文化の中でもてはやされていた当時にあって、回顧的に見るとやはり時代の制約を受けていても、的確な整理と紹介を務めたことの意義はあったのだろうと憶測。海外からの輸入を貪欲に続けていた時代は過ぎ去って、思想雑誌も輸入思想を取り上げなくなった今の方が豊かなのか退行的なのか考えて、神妙な気分。2013/12/18


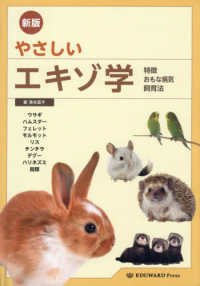
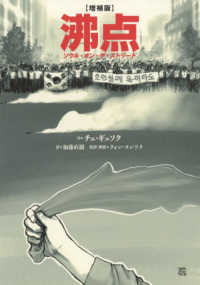
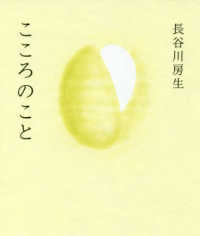
![シャーマニズム百科事典(全2巻)<br>Shamanism : An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture [2 volumes]](../images/goods/ar/work/imgdatag/15760/1576076458.JPG)



