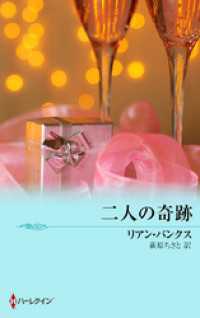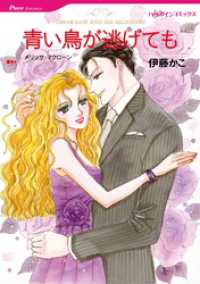出版社内容情報
【内容紹介】
廣松渉は、思想としての近代とはなにか、近代を超克するとはどのようなことがらであるのか、を哲学的に問いつめる。その若き日の主要論文をおさめたこの書は、「大きな物語」の終焉がささやかれる現在においてなお、新鮮なかがやきと衝撃力をうしなっていない。否、思想的指針の一切を喪失したかに見える今日にあってこそ、それらの論考の課題意識が十分にふまえられてなければならないとおもわれる。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
10
漢字の独特な用法をイジりたくなるイカつい哲学書。ある物体を角材として使うかゲバ棒として振り回すかは「〜として」見なす理念の意味付与で決まり、個々の事物は理念の肉化の役割を果たす。なので道具も人間もそこに意味-役柄が付与された演劇みたいになり、一定の音響がワンワンかそれともbowwowに聞こえるかも付与された理念的な意味次第。個人的主観に見えた物の意味理解は、構造主義も語るようにまず共同で構築されることを緻密に論証するが、この緻密さよりも共同幻想とかの曖昧だがキャッチーな概念の方が伝わり易いというジレンマ。2025/03/06
amanon
7
何かと問題はあるだろうが、一人の哲学者がこれだけのオリジナルティを有した思索を一冊の本にまとめ上げたということに改めて驚愕させられる。また、本書で提唱されている「主観ー客観」図式に代表される近代的世界観の超克はその後殆ど進展していない…というより、その問題意識さえ忘れ去れているのではないか?という気がしてしまう。そこには、本書の時代的背景にあった左翼運動が殆ど風前の灯火に状態にあり、マルクス主義も退潮の一途を辿っているという事情もあるのだろう。そうした背景をいったん不問に付して今一度読まれるべき一冊。2015/04/24
SE
3
前期ハイデガーに似ている。ただしハイデガー哲学があくまでも存在論なのに対し、こちらは認識論の書である。またハイデガーは本来的実存を一個の現存在にまで切り詰めて考えるが、廣松はそれを批判し、根底に共同存在をおく(ここは和辻に近い)。近代を超克せんとする点でも両者は共通するが、ハイデガーがマルクス主義をも排するのに対し、廣松はマルクス主義に依拠することで近代の乗り越えを図る。2018/04/12
Ex libris 毒餃子
3
非常に廣松2010/10/14
里のフクロウ
2
近代ヒュポダイムの超克を標榜して認識論を展開している。問題認識は20世紀中葉での哲学及び科学の閉塞である。その根源を近代認識論のヒュポダイムすなわち「主観-客観」図式にあるとし、新たな認識論を弁証法で構築していく。共同主観の論理は多岐にわたる課題を例の難解な言い回しで緻密に論証しているが、読み終わってみれば意外と全体像は理解できた。読後、新たなテーマを抱くことになった。独我論を超克する『共同主観』ではどのような世界が見えるのか。それは近代で見ることができなかったものなのか、それとも未知の新たな世界なのか。2016/10/13