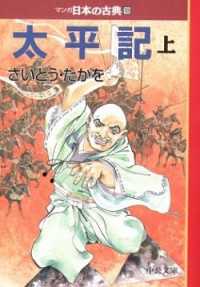内容説明
カゲロウ、イワナ、ウマ、ニホンザル、チンパンジー、ゴリラと研究対象を展開する一方、1500有余の山頂を踏査する中で構想されたものは、今西学と総称される生物全体社会を見すえた「自然学」であった。真のナチュラリスト今西錦司が前著『自然学の提唱』に引き続き展開する本書は、地球規模の問題が多発する今日、21世紀の日本と世界を透視する確かな視座を提示する万人必読の書である。
目次
混合樹林考
「自然学」の提唱に寄せて―2つの目の自画像
自然学に向かって
自然学へ至る道―自然の全体像―直観の思想
生態学と自然学とのあいだ
「自然学」への到達
『生物の世界』への回帰
自然学の一つの展開―odum生態学に寄せて
自然学から見たわが国の自然―生態学から生物地理学への復帰
生物社会学のことども―小田柿進二著『文明のなかの生物社会』の序
場の共有から共感へ
プロトアイデンティティ論
群れ生活者たち
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
50
著者82歳から85歳までの論文・エッセイを収めた実質的に生前最後の本。生涯の集大成といってよいだろう。この年齢で思い出話に留まることなく新たな学問の構築を企てようとしているところに驚嘆する。ダーウィンを批判した独自の進化論を唱えた人として有名だが、登山家(日本初のヒマラヤ遠征を企てるが戦争で中止)→生態学→昆虫→ウマ→霊長類→山岳論(未完)→自然学という軌跡が集約された感がある。ダーウィン批判、生態学批判、自然科学批判など理論的考察と、照葉樹林論など日本の自然学の構築。登山家としても学者としても自然と↓ 2015/08/10
-
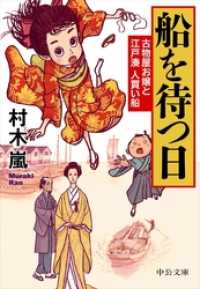
- 電子書籍
- 船を待つ日 - 古物屋お嬢と江戸湊人買…