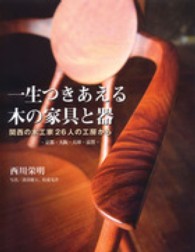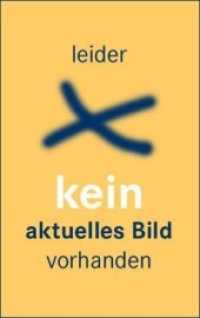出版社内容情報
【内容紹介】
キリスト教といえば西洋のものと考える人が多い。しかし、キリスト教初代からの伝統をいまなお保持しているギリシャ正教を知ると、その見方が誤まりであることに気がつく。ビザンチン文化やドストエフスキイの思想などを通して断片的に知られているにすぎないこのギリシャ正教の全貌を、本書はわが国で初めて体系的に紹介するとともに、西洋のキリスト教とその文化の原泉を問い、私たちの通念そのものをただす注目の書である
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
67
読友の紹介で手に取る。著者は正教の宗教者であり、西方のキリスト教より実践的というのは、身内にクリスチャン(新教)がいる者からすると、ちょっと決めつけを感じた。それより正教が良くも悪くもプリミティヴな信仰形態を残しているように感じられた。そういう意味では権力におもねいたカトリックとの違い(正教が権力に近づくことを「ハーモニー」と表現しているのが印象的)を感じ、歴史の中で苦難を受け(何しろ第4回十字軍ではカトリックにまで侵略を受けている)、それに耐えたあり方については理解できた。ドストエフスキーかぁ。。。2022/03/13
松本直哉
29
拝んでいるのは像そのものではなく像に表されたものだから、イコンは偶像崇拝ではない、というのはやはり詭弁ではないかと思う。著者は教会の中の人らしいからこういう書き方なのだろうか。文盲が大半だった民衆にとってイコンは聖書の代用品で、それなりの存在意義はあったのかもしれない。いずれにしても、偶像崇拝を厳しく禁ずるイスラームと隣合せに生きた正教会は、信仰や礼拝のあり方をめぐって何度も自問を余儀なくされただろう。一方、聖像を大量生産したカトリック教会は、そのような自問をしたことが一度でもあっただろうか。2022/05/10
シローキイ
29
ギリシア正教は通称東方正教と呼ばれ、ギリシャやそれを受容した南欧地域のセルビア・ブルガリア・マケドニア、東欧のルーマニア、ウクライナのキエフを首都としていたキエフ・ルーシのあった地域そしてジョージアで主に信仰されている。日本では明治時代ロシアの大主教ニコライによって伝わってきた。本書は日本人の司祭によって書かれていることもあってかなり詳しく歴史や儀式の形態知れる。特にギリシア正教と西方のローマカトリックとプロテスタントについても。そして本書はキリスト教の教えを知りたい人にもお勧めだ。2020/02/04
しろうさぎ
15
『カラマーゾフ』への言及が多いと聞き、未知の宗教の概要を知りたいと手に取る。高校の世界史は西欧と「西のキリスト教」中心なので、異なる視点の解説が新鮮。儀式の説明に画像での補足があれば良かった。もっとも東西の違いについては東への肩入れが強すぎると感じる。失われた「ビザンチン・ハーモニー」を絶賛しているが、政教一体化社会には賛否両論あろう(ゾシマ長老のユートピア信念でも同じ疑問をもった)。また米ソ冷戦末期の著作なので日本を含む世界情勢の捉え方が古く、ロシアとウクライナの軋轢のルーツも見えない。2023/08/10
彬
12
正教会の司祭である著者が、自身の属する正教会を日本へ紹介する。キリスト教でぱっと浮かぶのはカトリックとプロテスタント。よくよく考えればそれ関連のしか読んだことがなく、ギリシャ正教など全く考えたこともなかった。その点、日本でマイナーなことを自覚しているためか、ギリシャ正教の生き方、考え方、成り立ちなど事細かに分かりやすく解説している。著者が正教会の人なのでどうしてもそちら寄りの考え方になっており、「ギリシャ正教が本来のキリスト教」とスタンスを取っている。それを差し引いても正教会の入門書としておすすめ2012/05/17
-

- 和書
- 平成の愛唱寮歌八十曲選


![[To] the Last [Be] Human](../images/goods/ar/work/imgdatag/15565/155659660X.JPG)