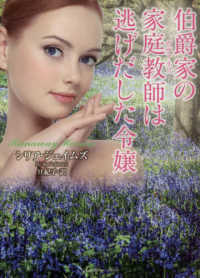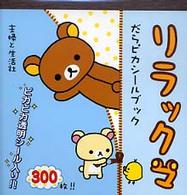内容説明
テレビゲーム、伝言ダイヤル、プリクラになぜ若者たちは熱中するのか。電子メディア社会の中で「遊び」はどう変容したのか。斬新な視点で論じつくす。
目次
第1章 “遊び感覚”とは何か(鳥と少年;「遊び」の簒奪;当世「お買い物ごっこ」考;笑いのエチカ)
第2章 「物語遊戯」の冒険(ホラーの快楽―ケースM;ポリゴンの迷宮―テレビゲームの快楽)
第3章 「メディアごっこ」の憂鬱(誘惑のミミクリー;「おたく」の反乱;ポストモダンの“わたし”探し;同調のメディア)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
nbhd
16
うすうす気づいてはいたが、ゲームのお勉強はしてるけど「ゲーム脳」「ゲームの影響で子どもは暴力的になるか?」論争や「ゲーミフィケーションで世界を変えるんだ」話には、興味がないということが僕のなかで定まった。99年発行のサブカル批評。著者はゲームにおけるプレイヤーとキャラとの「同一化」を共感や感情移入ではなく、「シンクロ(同期)」とさだめ、ゲームで獲得できるのは感情ではなく「行動感」だとする立場。論拠は弱いけど、ゲームのプレイヤーというメタ性を指摘している点で、貴重な先行研究かなと思う。2017/03/16
Kentaro
5
バブル期には、マスメディアを通じて盛んに、遊び心や遊び感覚といった耳当たりの良い言葉が喧伝されもした。消費の遊び心が美徳だとも言われた。しかし、バブルが弾け、阪神大震災を経験して、人生いつまでも遊んでいられないことも学んだ。そこで、当時の社会文化には、人生における豊かな遊びが欠けているということを伝えたかったそうだ。 昔の子供は犯罪とかけ離れたところで、いたずら、悪さを体感することができたが、今はそれができない。となりのうちの柿を盗んでも警察にも突き出されなかったが、今はスーパーでものをとれば犯罪である。2018/11/19
あかふく
3
1999年。大筋としては宮崎勤事件などによって大きく取り上げられた「現実の虚構の混同」の問題を単に少年少女たちのゲームという経験に帰することで非難するのではなく、大人も含む現代(日本)社会を背景とするものだと考えることで「おたく」などの問題を広く見ようとするもの。もちろん現代を問題にした本として今は古いが、虚構の経験における共感、同一化、感情移入の峻別などはゲームや映像など、フィクションについて考えるにあたって必ず注意すべき点が抑えられていて有益。もっと手堅くは同著者『イメージの修辞学』を。2014/02/25
茶幸才斎
2
遊びには、プレイヤーの間に、ルールとしての行為のやり取りの他に、笑顔や歓声または動作のシンクロのような、「これは遊びだよ」というシグナル交換が適宜発生する。それは、昔の鬼ごっこも、現代の電子メディアが媒介する遊びも同じである。この「メタ・コミュニケーション」の取り方と取りやすさは遊びによって異なり、何らかの形でこれに齟齬や喪失が生じると、遊びが遊びでなくなり、ときに騒動になる。「今の若いもんは。。。」という頭ごなしの内容でないのはよかった。2010/01/09
tora
1
脱自己化された人達の浮遊するコミュニケーションという視点は面白い(なんか他にもありそうな話だけど)ただ、豊かなな遊びがないと言っておいて、じゃあ豊かな遊びって何なのかという点に言及がないのがちょっと残念。2012/03/30