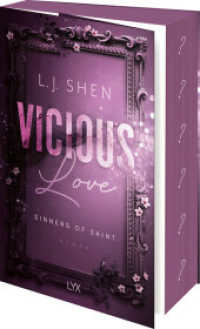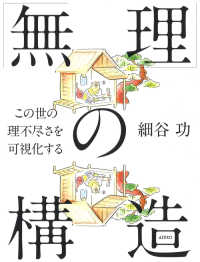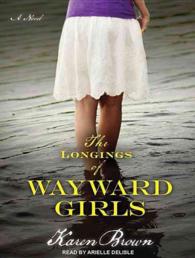内容説明
四〇〇年の時を超えて、いまなお伝統芸能の頂点に燦然と輝く歌舞伎。平成の世を迎えて、一気に華やぎを放射するその魅力の正体を、確かな審美眼で独自の美学を紡ぎつづける作家・赤江瀑が説き明かす。
目次
第1の章 歌舞伎の正体(弱肉強食の野に棲む巨大な怪獣;群雄割拠する平成歌舞伎)
第2の章 獅子の孤独(欲望という闘身に潜む空洞;役者の「土台」;魔法のような神通力の宇宙)
第3の章 歌舞伎の宝石(名優たちの去った野の後の光景;飽くなき女形たちの古典への食欲;色悪考)
著者等紹介
赤江瀑[アカエバク]
1933年、山口県下関市生まれ。日本大学芸術学部演劇科に在学中より、詩作、脚本などを手がけ、70年、「ニジンスキーの手」で第15回小説現代新人賞を受賞。74年に『オイディプスの刃』で第1回角川小説賞を受賞。83年に『海峡』と『八雲が殺した』で泉鏡花文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふくしんづけ
9
〈まず、食いついてみること〉とあるように、ここには専門的な内容を深掘りする意図はなく、著者の歌舞伎感、ひいては自身の著作にも通ずる芸術感に触れる内容である。なので歌舞伎ファンというより、著者目当ての読者向けの感は否めない。かくいう自分も資料的目的はちょっとあれどそのくちで、〈つかみ所のないものほど、本当は、つかみ所を無数に持っている〉など、あの作で読んだと通ずる価値観にニヤリする。2022/02/20
chobi
2
赤江瀑の最後の未読本(のはず)なので、読んでしまうともう新作が読めなくなると熟成させていた一冊。入門本にふさわしく平易な言葉の折々に赤江瀑だあ!という蠱惑的な表現がちらりちらり。そして、仁左衛門さんへの表現に膝を打つ。そそそそ!そうなんですよと。そしてこれが書かれた十二年後でも、その表現そのものですと、嬉しくなる。近々、新作ではないものの、千街氏の解説での出版があるらしく、元号が変わってしまったけれどもやっと読めた…。2019/08/18
garyou
1
時代が変われば人も変わるし人が変われば歌舞伎も変わる。江戸時代の歌舞伎といまの歌舞伎とは違うし、おそらく終戦直後の歌舞伎といまのそれとも違うだろう。変化についていけるかどうかだな、個人的には。ほんとうは書きたいことがあるだろうにズバリ書けない歯痒さのようなものを感じるのは深読みのし過ぎだろうか。襲名ラッシュの所以もちょっとわかった気がする。2019/01/21
ichiteru
1
歌舞伎入門とありますが全く違います。初心者にはオススメしません。個人的にも駄作。著者の歌舞伎論をずらずら述べているにすぎない。また、その文体も、小説家魂が変に入っているため、純文学のような華美な言い回しがいたるところに入り、また、話も脱線が多く、いちいち気に障り、鬱陶しくて不快。全く読むに値しない。2016/05/12
wang
1
現代の歌舞伎役者達に関する著者の雑多な感想や、雑学知識。著者も言っている通り多様な顔を持つ歌舞伎の世界はなにかとっかかりを決めないと全貌を語ることが難しい。それにしてもあまりに雑多すぎてまとまりがない。2010/11/12