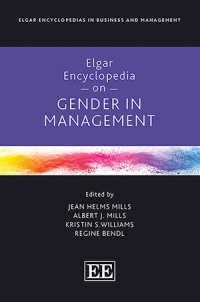- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
上手な「甘え」が子供を救う!壊れそうな子供・若者と親への緊急提言!土居健郎の未収録原稿を巻末に収録。
目次
第1章 現代に広がる人間関係の病
第2章「甘え」を喪失した時代
第3章 自然な「甘え」が生命力を育む
第4章 子どものカラダは崩れている
第5章 「甘え」が生み出す身体感覚
第6章 読書がつくる人間関係の理想
終章 日本人は「甘え」を失ったか
著者等紹介
土居健郎[ドイタケオ]
1920年東京都生まれ。東京大学医学部卒。東京大学医学部教授、国立精神衛生研究所所長を経て、聖路加国際病院診療顧問、医学博士。2009年7月永眠
齋藤孝[サイトウタカシ]
1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒。同大学大学院教育学研究科博士課程を経て、明治大学文学部教授。専門は、教育学、身体論、コミュニケーション論。著書に『身体感覚を取り戻す』(新潮学芸賞)『声に出して読みたい日本語』(毎日出版文化賞特別賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
レモン
40
「甘え」と聞くと確かに悪いイメージの方が先に来るが、良い意味での「甘え」がもっと許容される社会であってほしい。読書経験によって自分の感情と言葉とのズレが少なくなった、との記述には大いに同意できる。「ムカつく」にも色々な種類があるが、それを言葉で表現して他者に伝えられないなんて想像するだけでストレスが激しい。今までは論理的に説明されて納得することがほぼ大多数だったが、本書では抽象的なのに腑に落ちる、本質に直接語りかけてくるような感覚を味わった。2022/11/07
たる
20
「甘え」という言葉にどんな印象を持つか。 日本は戦後、欧米式のデモクラシーを取り入れて自由、平等、自立が国民全体に浸透した結果、甘えに対して否定的な感覚を持つようになってしまった。本来ノンバーバルなコミュニケーションを意味する甘え。親子関係においては人間のなつく時の感情であり、甘えを満たすことで自己肯定感を高める。大人になってもうまく甘えの雰囲気を作り出すことで人間関係を円滑に進めることのできる、高度な判断力を有する概念。「甘えはいわばひとつの技である」2016/05/05
ムラサキ
8
英語には「甘え」に相当する語がない。対して、日本は大和言葉より伝わるものである。言語により世界を捉える構造が変わるというのはソシュールも述べる。ソシュールは他国と比較してそれを論じた。しかし、現代では自国の言葉ですらその語彙は減少し話せなくなってきている。これは自分の認識する世界が空疎となることを意味する。このことが更に教養の狭まり、他者への許容範囲の狭まりに繋がる。家族構造の変革による、コミュニケーションの不足、家族を通した関係形成の機会の喪失がまた助長している。甘えを改めて考え直す時である。2023/02/15
Panico
6
定番『「甘え」の構造』エッセンス版とでもいうべきか。甘え関連の本に興味を持たせる導入としては役立とうもん。対談パートに長々とページを割いているが、そっちの方は「やっぱ若い奴はダメだな!」の一言でほぼ説明つきそうなくらいな雑談に過ぎない。まあそんなもんか2013/09/03
オリーブ
6
土居先生の「甘えの構造」の話が出てくるので、そちらを先に読めば良かったかな?と。子供は自発的に「甘え」るのであって、親が自分が気持ちいいからと「甘え」させてはいけないと言うのはなるほどな~と思う。子供が正しく甘えることが「安心感」に繋がり、そしてそれが「自己肯定感」に繋がるんですね。最後の方で「読書の大切さ」が書かれています。齋藤先生の言うように読書は言葉では言い表せなかったような自分の気持ちとそれを説明する言葉との間のズレを埋めてくれるものだと言うのも納得です。近いうちにまた漱石読んでみます。2013/08/06
-

- 和書
- 知里真志保 - 人と学問