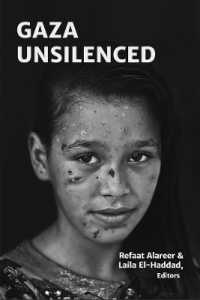出版社内容情報
日本人にも馴染みの深い「四大奇書」の『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』。出版バブルを迎えた明代後期は、人々が規範や常識を超えて、自分らしい人生を求めた、熱狂の時代だった。いかにして話し言葉による「白話小説」は生まれたのか。なぜアウトローが主人公で、反体制的なのか。作品を刊行した真の狙いとは何だったのか。元代から清代まで辿り、政治史・世界史からのアプローチも用いて、中国文学史の謎を解き明かす。
内容説明
日本人にも馴染みの深い「四大奇書」の『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』。出版バブルを迎えた明代後期は、人々が規範や常識を超えて、自分らしい人生を求めた、熱狂の時代だった。いかにして話し言葉による「白話小説」は生まれたのか。なぜアウトローが主人公で、反体制的なのか。作品を刊行した真の狙いとは何か。元代から清代まで辿り、政治史・世界史からのアプローチも用いて、中国文学史の謎を解き明かす。
目次
第一章 モンゴルの遺産
第二章 明代前期に起きたこと
第三章 寧王朱宸濠の反乱―戦争マニア武宗正徳帝と王陽明
第四章 新しい哲学と文学を求めて―陽明学と復古派
第五章 誰が、何のために『三国志演義』『水滸伝』を作り上げたのか
第六章 「南倭」と短篇白話小説集の出現
第七章 「北虜」と『金瓶梅』
第八章 熱狂の時代―出版の爆発的拡大と「真」の追究
第九章 祭の終わり―最後の輝きと明の滅亡
終章 その後のこと―消え去ったものと受け継がれるもの
著者等紹介
小松謙[コマツケン]
1959年、兵庫県生まれ。京都府立大学教授。専門は中国文学。京都大学大学院博士後期課程中退。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
電羊齋
さとうしん
ピオリーヌ
河イルカ
-
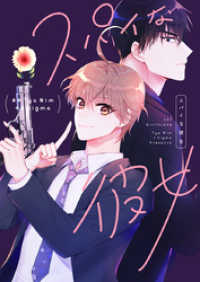
- 電子書籍
- スパイな彼女【タテヨミ】第39話 pi…