出版社内容情報
明治政府の掲げた国家目標とは何であったのか。それは、欧米諸国と向かい合い並び立つ、「万国対峙」が可能な近代国家となることであった。内実整備の実現に邁進した廃藩置県(1871年)から明治十四年の政変(81年)までの10年間は、万国対峙を目指してさまざまな道が模索された。西郷隆盛・木戸孝允・大久保利通の万国対峙策を検証しつつ、明治日本における国家構想の試行錯誤の道程を、相克の政治史として描き出す。
内容説明
明治政府の掲げた国家目標とは何であったのか。それは、欧米諸国と向かい合い並び立つ、「万国対峙」が可能な近代国家となることであった。内実整備に邁進した廃藩置県(1871年)から明治十四年の政変(81年)までの10年間は、万国対峙の実現を目指してさまざまな道が模索された。西郷隆盛・木戸孝允・大久保利通の万国対峙策を検証しつつ、明治日本における国家構想の試行錯誤の道程を、相克の政治史として描き出す。
目次
1 明治維新政府と万国対峙
2 留守政府と万国対峙
3 万国対峙をめぐる政変
4 大久保政権の成立と内務省
5 大久保政権と万国対峙
6 立憲制国家と万国対峙
著者等紹介
勝田政治[カツタマサハル]
1952年新潟県生まれ。早稲田大学卒業後、同大学大学院博士課程修了。国士舘大学文学部教授。専攻は日本近代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
16
明治維新から国会開設のの勅諭が出された1881年までの歴史を、「万国対峙」という政府のスローガンを軸に記述。内政・外交・産業政策に及ぶ詳細な明治初期の歴史を、ひとつの軸を通したことにより、かなり見通しの良いものになっている。特に岩倉使節団と留守政府、「征韓論」と明治6年政変、台湾出兵と江華島事件あたりの、政府内の対立と変化は整理されていて分かりやすかった。一方日清、日朝関係の評価は、限定された時代の記述のせいかちょっと曖昧な印象。逆に政府と民権運動の関係はかなり腑に落ちた。明治初期の政治史の好著だ。2018/04/17
かんがく
9
「万国対峙」をキーワードとして、軍事による対峙(西郷)、経済による対峙(大久保)、立憲による対峙(木戸)を軸に憲法制定までの明治史を概観。坂野潤治の「強兵派」「富国派」「憲法派」の分類と合致する。最近、この時代の本を読みすぎているからか新しい発見は特になし。2020/06/21
スプリント
4
明治維新の元勲たちが海外の先進諸国とどのように対峙していったのか。明治初期の動乱の政局と絡めながら説明しています。2017/10/11
dahatake
1
明治維新の推進組が万国対峙と称された対外政策として、日本という国家てしての政策論争を辿った話。富国強兵の「富国」部分は、その後の対外戦争での国力の無さや に繋がるし。軍力一辺倒の思考に陥りがちだった時代での経済・経営とのバランス感覚。これは今の事業にも通じる話しに思えた。2025/06/14
バルジ
1
「万国対峙」をキーワードに明治初期の政治史を概観している。内政・外交双方を視野に収め幅広く記述しているため、読んでいる途中に「万国対峙」という視点を忘れそうになってしまった。2017/10/13
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】悪役令嬢の発情期【タテヨ…
-

- 電子書籍
- 99万の前世が俺を覚醒させた【タテヨミ…
-
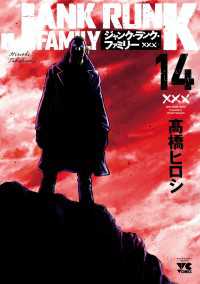
- 電子書籍
- ジャンク・ランク・ファミリー 14 ヤ…
-

- 電子書籍
- 胸キュンスカッとコミック版~君がいた夏…





