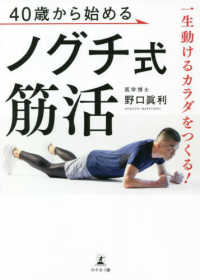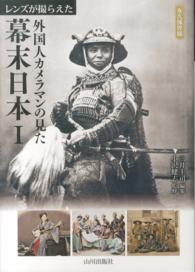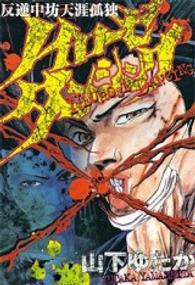内容説明
『遠野物語』は怪談への熱狂から生まれた―。明治後期、文明開化以来の合理主義と功利万能主義に抗うように噴出した怪談ブームと、柳田國男や泉鏡花らが熱狂した「怪談会」。その知られざる実態を、豊富な史実と文献でひもとき、名著誕生の経緯を怪談史の視点から探究。怪談実話としての真髄を明らかにし、芥川龍之介らを経て現代に至る怪談文芸の系譜を展望する。史上初復刊!「日本妖怪実譚」も収録。
目次
序章 怪談実話の見果てぬ夢
第1章 「怪談の研究」をめぐって
第2章 怪談ルネッサンス
第3章 泉鏡花と柳田國男
第4章 「遠野怪談」三人男
終章 遠野物語に始まる怪談史
復刻資料
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
36
明治からの精神医療などの西洋文化の導入から復古するかのごとく、盛んになる文豪たちの怪談会。初めに「同じ怪談を聞いていても聞き手によっては異なってくる」という記述からは柳田國男氏の『遠野物語』に対してその元ネタともなったことを話した佐々木喜善氏が憤慨したという理由の一端がつかめそうかも。泉鏡花氏の故郷での実話でもある『海異譚』への柳田國男氏との対談が興味深かったです。しかし、紹介されている怪談が概要だけなのと遠野での活動より東京の文豪たちとの繋がりがクローズアップされているだけなのが残念です。2013/10/12
ハチアカデミー
13
文壇における「怪談ルネッサンス」が巻き起こる中で刊行された書籍として『遠野物語』を捉え直すことで、民俗学が取りこぼしてきた異なる魅力を明らかにせんとした一冊。柳田と交流の深かった泉鏡花を軸に、近代の言説の中に『遠野物語』を落とし込むと、本書が「怪談」として書かれているという読みが可能となる。そこから、近代怪談史が見えてくる。鏡花の「遠野の奇聞」の引用も興味深い。柳田が後年、「妖怪」「怪談」というタームを頑なに避けたところからは、学者としての矜持が垣間見えた。終章記載のミニ怪談文芸年表はコンパクトで便利。2014/07/28
かっぱ
6
明治の文人墨客達による怪談ブーム。夜ごと開かれる怪談会に後の遠野物語の作者となる柳田国男の姿あり。柳田と泉鏡花などの怪談好きの作家達との交友関係がおもしろい。2013/01/12
HANA
6
遠野物語の発生を怪談の観点から読み解いたもの。怪談や百物語が盛んだった当時の空気や、柳田とそれらの繋がりが書かれていて面白く読めた。惜しらむは東京での動きが中心となっていて、遠野自体との繋がりが見えてこないこと。主題を考えれば仕方ないのかも知れないけど。2010/09/05
色々甚平
4
遠野物語を民俗学的にではなく怪談文学として捉えて書かれた本。明治の怪談文学の広がりや、怪談好きの作家たちの集まり、柳田が「怪談」という言葉を使うことに注意していた話など、当時のある一部の文学背景を見る分には面白い本だと思う。2013/05/20