内容説明
コメはいつから主食となり、肉はなぜ忌避されてきたのか。縄文時代の木の実から現代のハンバーガーまで、社会のシステムのなかで日本人はどんな食べ物を選び、どんな料理や文化をかたちづくってきたのか。祭祀・儀礼や宗教、政治・制度、都市の形成など、各時代の歴史背景と深いかかわりをもつ「食」。中世から近世にかけて築かれた「米社会」と、文化としての料理の発展など、日本の歴史に直結する「食生活」通史の決定版。
目次
“食”の重み―食生活史の視点
木の実の利用―採取と狩猟からの出発
米づくりと社会と文化と―水田稲作と国家の発生
“聖”なる米の選択―古代国家の水田志向
農業と自然―中世の農業と食生活
“穢”された肉―中世前期の食生活と宗教
米への希求―中世後期の食生活と差別
料理と政治―日本料理の変遷と儀式
米社会の完成―近世食生活の位相
茶懐石の発展―近世料理文化の形成
“遊び”と料理―近世料理文化の爛熟
西洋料理のはじまり―近代への移行と食生活
近代化と食糧制度―世界大戦と食生活
ハンバーガーの登場―現代社会の食生活
著者等紹介
原田信男[ハラダノブオ]
1949年生まれ。国士舘大学21世紀アジア学部教授。明治大学大学院博士後期課程退学、博士(史学)。ウィーン大学客員教授・国際日本文化研究センター客員教授・放送大学客員教授を歴任。専攻は中世史、食文化史。著書に『江戸の料理史』(中公新書、サントリー学芸賞受賞)、『歴史のなかの米と肉』(平凡社ライブラリー、小泉八雲賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
はるほのパパ
猫
レコバ
リュウジ


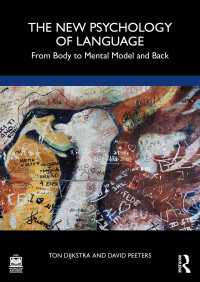
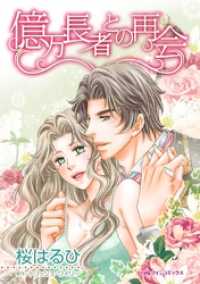

![えいごにほんごおうたえほん わくわくおとあそびえほん [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48857/4885742579.jpg)



