出版社内容情報
柳田 国男[ヤナギタ クニオ]
著・文・その他
内容説明
児童の言葉や遊びを民俗学的に論じた表題作ほか、「こども風土記」「母の手毬歌」「野草雑記」「野鳥雑記」「木綿以前の事」の六作品を収録。幼少期の純粋な好奇心を生涯持ち続けた柳田国男。そのみずみずしい感性と、対象への鋭敏な観察眼が伝わる傑作選。
目次
小さき者の声
こども風土記
母の手毬歌
野草雑記
野鳥雑記
木綿以前の事
著者等紹介
柳田国男[ヤナギタクニオ]
1875年、兵庫生まれ。1900年、東京帝国大学法科大学卒。農商務省に入り、法制局参事官、貴族院書記官長などを歴任。35年、民間伝承の会(のち日本民俗学会)を創始し、雑誌「民間伝承」を刊行、日本民俗学の独自の立場を確立。51年、文化勲章受章。62年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
40
子供の世界や庭先に見られる小さな自然等を題材に、そこから思索を広げていく論考が収録されている。「小さき者の声」であれば「ののさま」「まんまいさま」の言葉を読む度、あの遠い夕暮れに見上げた満月を思い出すし、「こども風土記」であればそこに収録されている数々の遊びから子供の頃の数々の遊戯を思い出させられる。幼児の言葉も遊戯も手毬唄も、収録されている全てがノスタルジアに直接訴えかけてくるように感じた。その他も庭先の草花や小鳥の鳴き声等、全て小さな事から始められており、その意味で本書全てが「小さき者の声」であった。2013/04/04
シュエパイ
8
表紙がとっても綺麗なので読んでみようと思い立ちました。子供たちの文化風土記、って感じなのかな?きっと、もう失われたり、受け継がれてたり、現代風に姿を変えたりしてる遊びたちなんだろうな。ノノサマ、だけはなんか聞いたことあるな?小1のころ、保育園児だった私以外の子は全員、2つの幼稚園のどっちかの所属で。片方の勢力の子が、「ノノサマは口では何にも言わないけれど♪」って歌ってたっけ。懐かしいなぁ、よく余所者扱いで苛められては殴り返してたんだっけ♪2013/11/11
roughfractus02
7
山人と南島からの渡来人が混交する常民への関心は、国家が多様で層を成すこ点を露わにする。本書は、人間という観念の重層性について、子供という異質な存在を資本主義的な枠組みで、大人なる観念に取り込む政治を、子供の言葉、遊び、母の子守唄やこども組の分布と青年団の制度的関係からネットワークの広がり方とに注視して検討する。その中で、手毬唄に見られる鞠の材料である木綿の生産と普及に注目する著者は、元禄期の『芭蕉七部集』から文化文政の資料へと見渡しながら、定住者の生活を山伏、島流し、遊女ら移動する人々の生活から捉え直す。2025/02/18
寝落ち6段
3
日本の原型とは何か、それを子供の遊びから考察した一冊。地域によって風土は全く違うのに、遠く離れた土地で似たような遊びや言葉を使っていることがある。現在ではもう見られない遊び・言葉は貴重だ。あれこれと世界を知らない子供は純粋にその地域で育ち、意識しないままその世界のみを生きる。それ故に純粋にその地域の特性を持ち合わせている。そう思うと自分の子供のころはどうだったかなあと耽ってしまう。2013/06/09
Schuhschnabel
2
ままごと遊びは意外と奥が深いんだなあという陳腐な感想はさておき、全体を通して何をしているのかがわからない。『青年と学問』にあるように、世の中の役に立つことを目指すのが民俗学の存在理由だと思っているのだが、「木綿以前の事」を除いてはその道筋がイメージできなかった。一方、純粋に資料として残そうとしたのなら柳田の解釈が含まれすぎているように感じる。あと、歌はメロディーがわからないので、歌詞だけ書かれてもどう歌われたかイメージできない。2021/03/16
-
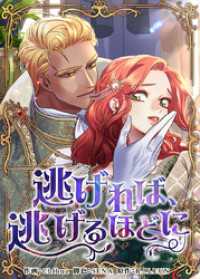
- 電子書籍
- 逃げれば、逃げるほどに【タテヨミ】第6…
-

- 電子書籍
- ドS騎士団長のご奉仕メイドに任命されま…







