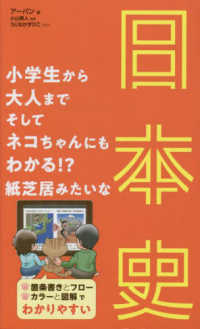出版社内容情報
日本民俗学の巨人が著した最晩年の名著復刊!
日本民族の祖先たちは、どのような経路をたどってこの列島に移り住んだのか。表題作のほか、海や琉球にまつわる論考8篇を収載。大胆ともいえる仮説を展開する、柳田国男最晩年の名著。
内容説明
日本民族の祖先たちは、どのような経路をたどってこの列島に移り住み、いかなる技術・宗教・習俗を運んできたのか。表題作のほか、海や琉球にまつわる論考八篇を収載。大胆ともいえる学問的仮説を展開し、後世の幅広い領域に多大な影響を与えた最晩年の名著。
目次
海上の道
海神宮考
みろくの船
根の国の話
鼠の浄土
宝貝のこと
人とズズダマ
稲の産屋
知りたいと思う事二、三
著者等紹介
柳田国男[ヤナギタクニオ]
1875年、兵庫生まれ。1900年、東京帝国大学法科大学卒。農商務省に入り、法制局参事官、貴族院書記官長などを歴任。35年、民間伝承の会(のち日本民俗学会)を創始し、雑誌「民間伝承」を刊行、日本民俗学の独自の立場を確立。51年、文化勲章受章。62年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
-

- 洋書
- KIF-KIF
-
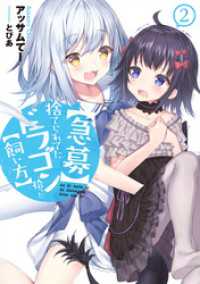
- 電子書籍
- 【急募】捨てられてたドラゴン拾った【飼…