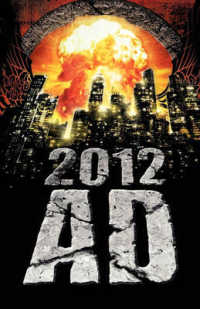出版社内容情報
神崎 宣武[カンザキ ノリタケ]
著・文・その他
内容説明
俳句に季語があるように、季節の移ろいに敏感な日本人。かつての日本には、春夏秋冬の四季のほかに、夏の土用を含めて季節の変わり目としての4つの土用があり、「旬」という豊かな季節感をはぐくんできた。今もフキノトウや花見に春、初鰹や端午の節供に初夏、虫の音や新米に秋、餅つきや冬至に冬を感じるのはなぜか。現代人が忘れてしまった文化としての「旬」、まつりや行事に映る多様な「旬」の文化を民俗学的に読み解く。
目次
1 春(鏡餅と雑煮;餅なし正月 ほか)
2 夏(端午の節供とショウブ;ちまき ほか)
3 秋(虫聞き;月見 ほか)
4 冬(亥の子;寒仕込みの酒 ほか)
著者等紹介
神崎宣武[カンザキノリタケ]
1944年生まれ。民俗学者。旅の文化研究所所長、岡山県宇佐八幡神社宮司(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けっち
2
四季の移り変わるの中で生活して、自然の神と共に生きていきている事を再認します。 昔からの町の行事が 盆踊り、鏡餅、 除夜とか始まりの意味が判り考えては参加してみます。2010/12/15
ishicoro
1
砂糖が普通に使えるようになったのも台湾を統治していた100年ぐらい前から、それ以前は餡子を使った菓子は貴重なものだったんですね。鳥や虫の声を賞でる機会って田舎に行くと良さが分かるのですが都会生活してると季節を味わうことが減っているのでもっと季節の楽しみに目を向けてみようと思うのでした。そろそろ梅雨だし紫陽花とか楽しみたいものです。2019/06/07
YOS1968
1
四季折々の行事の意味など、歴史文化的背景を教えてくれる優れた本である。自然との共存、神々との対話、節目節目での行動規範。積み重ねてきた歴史の意味は深く、それを知らずに生きている自分が、ちょっと恥ずかしくなっちゃったりする。また読み返したくなるだろうと思わせる本です。2011/10/12
びいたな
0
四季、および四季それぞれにある土用(移り変わりの時季)についての慣習や文化について紹介をしている。多くは「今の若い人」にとっては聞き馴染みのないものだったり、失われつつあるもの。そのこともあり、どうしてもそれぞれの紹介文の最後の一言には「嘆き」の色が多くでていて、現代人としてなんとなく肩身の狭い気もしないではないが、確かに季節感豊かな折々の文化を知る人がそれを惜しむ気持ちはわかる気もした。読み手としては年配の方を想定しているように感じつつも、得られる知識は新鮮で面白かった。2012/09/02
-

- 電子書籍
- BMW BOXER Journal V…
-
- 洋書
- 2012 AD