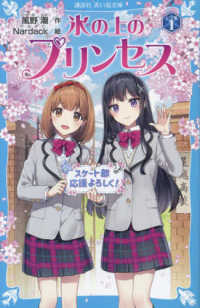内容説明
古代のモダン食品だった団子、大仏とソラマメの意外な関係、豆腐料理が大変身したおでん、イスラームの菓子だったがんもどき、下魚として嫌われたマグロ、ハクサイと日清戦争など、思わず「ヘエー」と驚く身近な食材と料理にまつわるウンチクを大公開。『「食」の世界史』の著者が、世界の動きとともに日本の食文化がどのように組み替えられてきたかを語る、雑学的な一口話としても読みごたえのある、歴史と文化の面白日本史。
目次
第1章 古代からの豊かな「食」
第2章 大陸からきた「食」の文化
第3章 「食」のルネサンス、室町時代
第4章 ポルトガルとオランダが運んだ「食」
第5章 江戸時代につくられた食文化
第6章 「洋食」の誕生と世界化する食卓
著者等紹介
宮崎正勝[ミヤザキマサカツ]
1942年生まれ。元北海道教育大学教育学部教授。東京教育大学文学部史学科卒。専攻は、前近代の国際交流史、世界史教育(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
28
面白かった! この本には今日本人におなじみの食文化がどう伝来・発展し、定着していったかとても丁寧に書かれている。ういろうが元は消臭剤だったこともびっくりだったし(今食されているものとはルーツが違う)、がんもどきがイスラムのお菓子だったとは! 現在の私たちの食卓に並ぶものがいかに海を越え、姿かたちを変えてきたか、実にロマンがあり、良い本だった。2013/09/04
タルシル📖ヨムノスキー
25
以前読んだ永山久夫さんの〝日本人は何を食べてきたのか〟をもっとフランクにしてエンタメ感マシマシにした感じの本書。取り上げているのは穀類や野菜、調味料に始まり、うどんやそばなどの麺類、きんつばやかりんとうなどのお菓子類、餃子やワンタンなどの中華料理、コロッケやハンバーグ、カレーなどの洋食、そしてカルピスやコーラまで幅広い。日本人は昔から日本流にアレンジするのが大好き。何よりも驚くのは農水省が2008年に発表した国内生産の食材のみで1日ひとり2020kcalを確保するための献立。コレは衝撃的。大丈夫か日本?2023/12/22
黒猫
17
縄文人が一番食べていた貝はハマグリだったのか。アサリとかだと思っていたが、ハマグリを食ってたんだなー。なんか親近感が沸く。焼き蛤にしたり茹でて食ってたのかな。いわしなんか食い放題だったろうなあ。仏教文化が広まった奈良平安時代には肉は食べられなかった。タンパク質を肉ではなく遣唐使が運んできた乳製品で取られた話はなかなか面白い。貴族にチーズはもてはやされモダンな食べ物として醍醐味なんて言われていたんだな。出汁や、豆腐等今でも日本食で使われる食べ物は、東山文化の時期に大成した。いろいろ勉強になる。2021/08/23
ヨハネス
9
なかなかおもしろかったです。「食」というひとつだけの興味を軸に、日本の歴史はもちろん、世界の歴史、文化、日本語の古語までさまざまな分野にわたり起源を勉強できます。例えば家庭ですき焼きをしたら、小学生の子供にものすごくたくさんのことを教えられそうです。江戸時代の人が大変高価な初ガツオを競って手に入れたのは、脂の乗った魚は当時の人の口に合わなかったからなんですってー。だからまぐろのトロも捨てられたわけね、きっと。2015/01/28
たかしくん。
9
読みやすいばかりでなく、予想以上に、これまで知らなかったことが、記述されていて、面白かったです。2012/07/21
-

- 和書
- 現代語 処世の大道
-
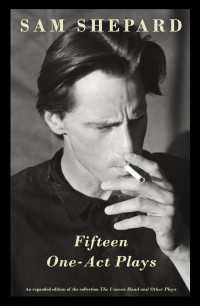
- 洋書電子書籍
- Fifteen One-Act Pla…