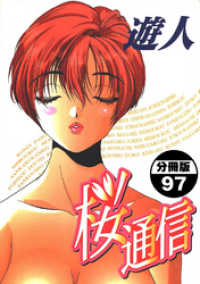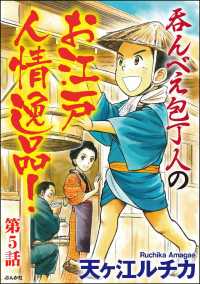出版社内容情報
「宇野は、マルクス経済学とマルクス主義経済学を区別した。マルクス主義経済学は、資本主義から社会主義への転換は必然であるとする、唯物史観というイデオロギーによって革命に資する経済学を構築する試みだ。これに対してマルクス経済学は、アダム・スミス、デービッド・リカードら、古典派経済学を批判的に継承したカール・マルクスが、『資本論』で展開した理論を基礎にして資本主義の内在的論理をとらえる体系知(Wissenschaft、科学)である、というのが宇野の主張だ。」
――佐藤優氏(解説より)
日本の代表的マルクス経済学者宇野弘蔵。
宇野はマルクスの『資本論』を批判的に読み込み、その理論とイデオロギーを分離した。
その上で経済学の研究を原理論、段階論、現状分析の3段階に分けて独自の経済学を構築し、その理論は大きな影響を与えた(宇野学派)。
宇野弘蔵が宇野派を代表する研究者と共に、大学の教養課程における経済学の入門書としてまとめたのが本書である。
数多の経済学徒を導いたロングセラーを復刊!
※本書は1956年3月(上巻)、4月(下巻)に角川全書から刊行された作品を復刊し、図表を再作成し、解説を加えたものです。
内容説明
日本の代表的マルクス経済学者宇野弘蔵。宇野はマルクスの『資本論』を批判的に読み込み、その理論とイデオロギーを分離した。そして、経済学の研究を原理論、段階論、現状分析の3段階に分けて独自の経済学を構築し、彼の理論は大きな影響を与えることになる(宇野学派)。宇野が学派を代表する研究者たちと、大学教養課程における経済学の入門書としてまとめた名著を復刊!数多の経済学徒を導いたロングセラー。
目次
序論
第1部 資本主義の発達と構造(封建社会とその崩壊;資本主義の発生;資本主義社会の確立;後期資本主義への転化)
第2部 経済学説の発展(序説;一七世紀の経済学;一八世紀の経済学;古典経済学の確立とその解説)
著者等紹介
宇野弘蔵[ウノコウゾウ]
1897年、岡山県生まれ。1921年、東京帝国大学卒。東北帝国大学助教授を経て、東京大学、法政大学などの教授を歴任し、77年に死去。経済学博士。マルクス主義経済学を専門とし、その独創的な『資本論』読解により、宇野学派と呼ばれる学派を形成した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
樋口佳之
元よしだ
amanon
モッチー


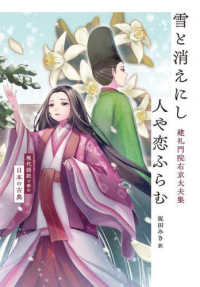
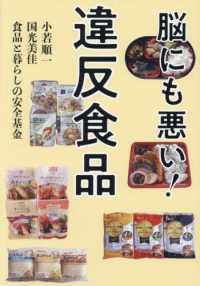
![[音声DL付き]CNN ENGLISH EXPRESS 2021年7月号](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1006599.jpg)