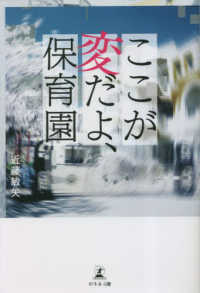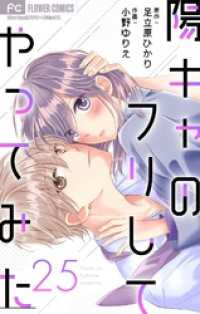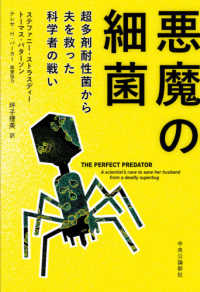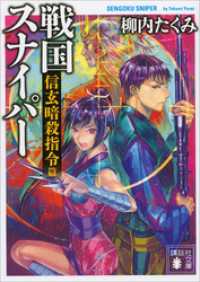出版社内容情報
鴨 長明[カモノ チョウメイ]
著・文・その他
簗瀬 一雄[ヤナセ カズオ]
著・文・その他
内容説明
枕草子・徒然草とともに日本三大随筆に数えられる、中世隠者文学の代表作。人の命もそれを支える住居も無常だという諦観に続き、次々と起こる、大火・辻風・飢饉・地震などの天変地異による惨状を描写。一丈四方の草庵での閑雅な生活を自讃したのち、それも妄執であると自問して終わる、格調高い和漢混淆文による随筆。参考資料として異本や関係文献を翻刻。
目次
ゆく河の流れは絶えずして
玉敷の都のうちに、棟を並べ
知らず、生れ死ぬる人
予、ものの心を知れりしより
去安元三年四月廿八日かとよ
火元は、避口冨の小路とかや
人のいとなみ、皆愚なる中に
また、治承四年卯月のころ
三四町を吹きまくる間に篭れる家ども
辻風はつねに吹くものなれど〔ほか〕
著者等紹介
簗瀬一雄[ヤナセカズオ]
1912年‐2008年。東京生まれ。早稲田大学卒業。文学博士。豊田工業高等専門学校・豊橋技術科学大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
71
短く読みやすかったが、内容はかなりシビア。平家の台頭で政情が不安定になっただけでなく、大火、地震、辻風とますます不安定になっていく世情が冷静な目で描かれている。天災に慌てふためくの町の様子を客観的に描写するのも、「人の営み、皆愚かなる中に、さしもあやふき宮中の家をつくるとて、宝を費し、心を悩ます事は、すべてあぢきなくぞ侍る」とつづるのも、鴨長明の無常観だ。平家の動向をあえて描かないのも、そのためか。2017/10/13
藤月はな(灯れ松明の火)
48
時は末法。天変地異に襲われる日本へ「ああ、諸行無常だ、人間の営みなど、自然の前では虚しい・・・」と溜息を吐きつつも泡のように浮き上がってくる不安を愚痴るは、鴨長明である。兼好法師が人々の営みを常にチャックし、愛のある辛口コメントをする方ならば、鴨長明は人間の営みを危機に陥らせる時事に敏感過ぎるが故のネガティブ&悟り発言連発で読者が「大丈夫か、この人・・・」と心配になる方だろう。時代が変わっても発言者にこういう人がいることは変わらないんだな。しかも最後の隠居宣言は唐突すぎて心配過ぎる・・・。2017/06/09
ゆずきゃらめる*平安時代とお花♪
35
[日本の古典を読む第十回方丈記]のイベントより♪頑張って自分で原文も読みました。現代語に近い言葉が多くて読みやすかったです。本書は大福寺本を主としていますが参考資料の略式本も面白かった。比べてみるとちょっとずつ違いが分かる。方丈記全体を読むと長明の世のなかにいたたまれなくのがよくわかります。世を捨てても好きなことは捨てれないのが人。2017/10/09
sasara
28
ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。 教科書で有名鴨長明「方丈記」1212年著。解剖学者養老孟司さんがオススメしてたので読んでみました。鴨長明は下鴨神社の由緒正しい家系が父死亡後親類に疎まれ転落し出家。 地震大火飢饉など天変地異を克明に描写財産や地位があったとしても明日のことなど分からないので執着を持たず生きることが大切だが齢60前になってもなかなか捨てきれないと吐露する。平安時代も現代も人の本質は変わってないのかも 2021/08/05
Kepeta
18
現代語訳がべらんめえ過ぎるのが少し気になるが、読み易いのは助かった。これ、鴨長明って決してポジティブな形で隠遁生活を始めた訳じゃないよなあ...方丈での生活に安らぎを見出しているのは本当だが、一方で「俺の人生これでよかったのか」的な未練が振り払い切れていないのが行間から滲み出ている。そしてそんな自分を仏教的な意味での諦めの目線で見ようと努めている事も。器用貧乏だが知的で繊細な生身の人間の声として、聖人君子の言葉より切実に響くものがある。そんな中、僅かな記述だが山番の子との交流が詩情に溢れていて心温まる。2017/01/11