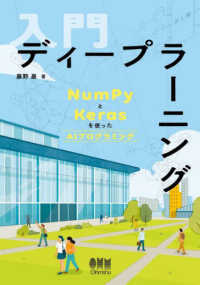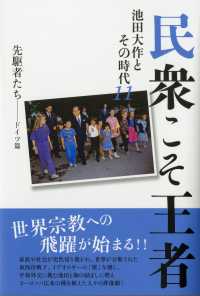内容説明
難攻不落のベーリング海峡を渡るには、徒歩かカヤックしかない。複雑な潮流や烈風、濃霧という劣悪な環境。ロシア側の上陸許可も下りていない。果敢にも大昔の人々と同じ徒行を試みるも、海峡が凍結せず惜しくも断念。先住民の協力を得てウミヤックで再挑戦するが、プライドの高い彼らとの衝突により、海上でリタイアさせられてしまう…。自然の驚異や先住民との軋轢を乗り越え、人類の英知をかけて進む、壮大なる旅の第3章。
目次
西部アラスカ犬ゾリの旅
ベーリング海峡徒歩横断を目指す
捕鯨の島セント・ローレンス島
海峡横断に挑戦
アラスカ各地を訪ねる
ワナ猟師ハイモ・コース
犬ゾリの旅を前に
犬ゾリの旅二〇〇〇キロ
狩猟民と共に
エンメレン村のセイウチ祭り
ツンドラ徒歩旅行
北の先住民と過ごす
著者等紹介
関野吉晴[セキノヨシハル]
1949年東京都生まれ。一橋大学法学部、横浜市立大学医学部卒業。93年から、あしかけ10年をかけ「グレートジャーニー」を踏破した。2004年から「新グレートジャーニー日本列島にやって来た人々」をスタート。99年、植村直己冒険賞受賞。現在、武蔵野美術大学教授(文化人類学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えっくん
20
★★★★☆第3巻はアラスカからベーリング海峡を渡り、ロシアのツンドラ地帯へ。ベーリング海峡をカヤックで渡る場面はTV放映時に見てグレートジャーニーの壮大さに魅了されたきっかけでした。犬ゾリで駆けたツンドラ地帯は-40℃の世界で、冷凍庫よりも過酷な環境が自然界に存在しているのが驚きです。訪問先の先住民の暮らしの紹介でトナカイや鯨、セイウチを捕らえ、解体し食する場面がありました。人間は生きるために他の生物を食さなければならない罪深い存在ですが、捕鯨問題を抱える日本人として食文化を守ることの大切さを感じます。2016/05/04
piro
8
アラスカからベーリング海を渡り、北東シベリアへ。『夏はユーコン川でサケを、秋はデナリ国立公園でブルーベリーを…グリズリーと同じものを食べてきたことに気が付いて、なんだか嬉しくなった。』アラスカの自然を体感する嬉しさが伝わってくる一節でした。ベーリング海横断は旅中盤のハイライト。渡り切った時の感慨が伝わります。そしてシベリア。ソ連時代にスノーモービルを使っていた人々が犬ゾリを使うようになったと言うのは何とも皮肉な話。あとがきで、親交があった星野道夫さんについて関野さんが語っているのにジーンときました。2018/03/21
tsubomi
4
2015.11.04-11.17:ベーリング海峡を渡ってシベリア平原を行く旅のレポート。北米からロシアへと旅する著者らは途中で現地の少数民族と一緒に船に乗ったり漁をしたり犬ぞりを走らせたり。。。アラスカの原住民が金の猛者のようになっている姿は悲しかったし、捕鯨の様子を撮影しようとすると神経質になってイライラしたりする現状も日本の捕鯨の現状と似ていて考えさせられました。後半、ロシアに入ってからは人々が貧しいながらも素朴で昔ながらの漁をしつつ、外部の人を歓迎している様子が伺えてホッとしました。2015/11/17
michu
4
人類の逞しさをビリビリと感じる。息子世代の誘いも断り、線量の高い土地に住み続ける福島の高齢者達に思いが行った。文化への、社会への、そして大地への愛着。理屈ではないのだろう。この巻は今までにもまして、自然環境の厳しさを感じると共に現地の人々との出会いが印象強く残った。助け合わなければ生きていけない環境。それこそが人間を最も人間たらしめるのだろうか。人の間と書いて人間。こんな所で本ばかり読んでいる私は果たして人間なのだろうか。ただの人でしかないのではないか。そんな中二病が発病しかねない危険な書。大好き。2012/07/10
マーク
3
41 少数民族との触れ合い、感動作。2016/04/13
-
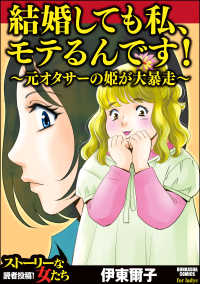
- 電子書籍
- 結婚しても私、モテるんです! ~元オタ…