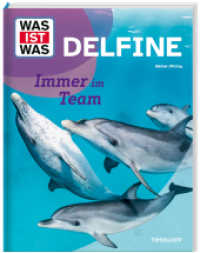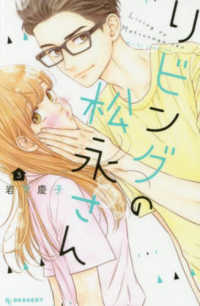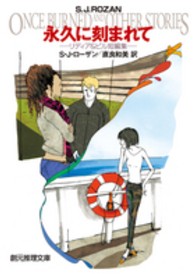内容説明
多彩な渡り鳥が飛来する池のほとりで暮らす千亜子。夫は老母の介護で実家に帰ったままだ。子供たちも出て行った。カラスのクロウと語り、林の生き物たちと交流し、牛飼い少女の物語の翻訳に打ち込む日々は、悪くはない。人道という偽善に付き合うよりも、生物としての死に場所を探したいからだ。美しくも激しい自然の中で、生と死に深い独自の眼差しを向けた新たなる感動小説。
著者等紹介
加藤幸子[カトウユキコ]
1936年、札幌生まれ。41年から47年まで中国・北京に滞在。北海道大学を卒業後、農林省農業技術研究所、日本自然保護協会勤務を経て、作家になる。83年、「夢の壁」で芥川賞、91年、『尾崎翠の感覚世界』で芸術選奨文部大臣賞、2002年、『長江』で毎日芸術賞を受賞する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
76
芥川賞作家加藤幸子さんの2003年の作品。あまり話題にならなかったようだけどこれは傑作だと思う。池のほとりに住む初老の女性の翻訳家が主人公。自然と同化してゆったりと生きる主人公の生き方が魅力的。自分の枠の外に出て猫やカラスと彼女が会話する場面はユーモラス。とは言っても非現実的な物語ではなく、夫の母の介護の問題などもしっかり書き込まれている。最後の場面で描かれる癒しは感動的。ここで描かれているように自然には人のこころの傷を癒す力があると思う。人も動物も草木もみんな同じ地平に立っているのだから。2013/11/03
翔亀
45
これは驚き。芥川賞作家だが1983年受賞と古く、寡作の為か知らなかったが、鳥つながりで巡り合った幸運に感謝したい。私の目下の関心事である鳥が31種類も出てきて大満足なのだが、文学として鳥抜きで感動的なのだ。本作は2003年、作家67歳の作で、主人公は作家の分身と思しい。都心の池の辺の古い家での老後(といっても精神は若々しい)の生活。夫が実母の介護で家を空け、独居の静謐な生活の四季が描かれる。自然に囲まれた晴耕雨読の生活みたいだが、自然の描かれ方が決定的に違っていて、文字通り世界を見る眼が一変する。2015/02/27
ハチアカデミー
13
加藤幸子、恐るべし。夫が母の介護をするため別居をすることになった女性の日常が描かれる作品なのだが、世界の見え方、描き方が尋常じゃない。クロウと呼ばれる鴉との交流(会話もする)が挟まれることも独特だが、作品全体の時間の感覚や、人の生と死に関する感覚が、なんというか違うのだ。小説作品なのだけれどストーリーではなく詩的言語を味わうような、最終章である「月下走馬灯」では語り手の脳内の時間旅行を追体験させられるような、そんな読書経験でした。凄い! と思うのだがその凄さが言語化できないので気になったら読んでください。2015/08/12
sarie
4
連作短編集6話。老母の介護で実家に帰ったままの夫と、池のほとりで暮らす主人公の初老の夫婦の日常を綴ったお話。 カラスと会話が出来たりする少し不思議な世界観の中で、夫婦のあり方などを淡々と描いた感じの物語でした。2015/11/15
yamakujira
1
ある初老の夫婦のかたちを、妻の視点から描く。なかよく見えても夫婦って結局は他人なんだとか、長年連れ添った夫婦だけにわかる呼吸ってあるんだとか、思わせてくれる。クロウの存在が釈然としないなぁ。 (★★★☆☆)2013/11/22
-

- 電子書籍
- 異世界でスキルを解体したらチートな嫁が…
-
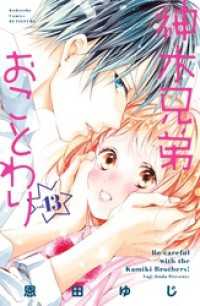
- 電子書籍
- 神木兄弟おことわり 分冊版(13)