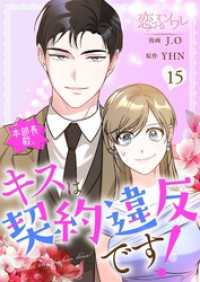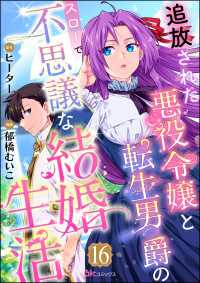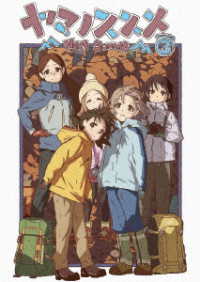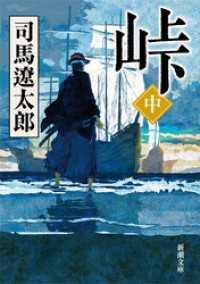内容説明
人は何のために生きるのか。苦しみと悲しみの極にあるとき、人はどのように生きる意味を見出せばよいのか。人間の「生きがい」について深いまなざしを注いだ精神科医・神谷美恵子。彼女自身も様々な苦悩や葛藤のなか、生涯をかけて自らの生きがいを懸命に追い続けていた。その日記にはときに自分らしい生への熱く激しい渇望が、ときに日常にひそむ人生の静かな喜びが、いきいきと語られている。人が本当に生きるとはどういうことなのか、読む者の心に深く問いかける真摯な魂の記録。
著者等紹介
神谷美恵子[カミヤミエコ]
1914年生まれ。精神科医。1935年津田英学塾卒、コロンビア大学に留学。1944年東京女子医専卒。東京大学医学部精神科、大阪大学医学部神経科勤務を経て1960年神戸女学院大学教授。1957~72年長島愛生園精神科勤務。1963~76年津田塾大学教授。医学博士。1979年没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
124
神谷さんの作品はいくつか読んでいるのですが、前田多門がお父さんで、前田陽一先生がお兄さんであることは知りませんでした。死の直前までの40年間にわたる日記です。その時々においてのご自分や家族などのことを中心に書いておられます。非常にストイックというか禁欲的な感じがしました。ある意味頑固な面もお持ちであった気がします。2018/03/13
meg
38
考え抜くこと。大切なことを書いてある。神谷美恵子氏の偉業の中に日常というあたりまえがあって。それがまた救われる。すばらしい本。2024/09/01
のんぴ
36
「楽しまなきゃね」が合言葉の私たちとは対極にいらっしゃる方。人への献身を使命とし、ご自愛ではなく、全ての人に心からの愛をささげる。多方面へのあふれ出る才能を持て余し、巻き込まれたり葛藤しながら、自分がやりたいこと、貢献できることを追及していく様子は、時間、体力との戦いでもあり、痛々しいほどだ。神谷美恵子さんの著作にふれると心が洗われる。2023/09/09
Miyoshi Hirotaka
26
恵まれた知的環境の中で育った才媛かつ良妻賢母の職業人。全てに完璧を求めた希求の人。明治期に復活したキリスト教の系譜では二世代目。国際連盟事務次長の新渡戸稲造と少女期に交友あり。偶然だが、恵泉女学院の創立者河井道も札幌農学校時代の新渡戸稲造と接点がある。この三人に共通するのは『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で近代資本主義の源流とされ、公の精神や職業倫理の形成に寄与したクエーカー派の禁欲的な教えの影響。成果は三人三様だが、女子教育の分野で己の才能を利他へと最大化する方向に作用したことは興味深い。2025/07/04
たまご
23
神谷恵美子が25歳から亡くなる3ヶ月前まで書き続けた(!)日記本。遺族が著者の死後に抜粋して本にしたとのこと。神谷氏は生涯「書くこと」で内省を繰り返していたため、日記には取り繕うことのない本物の文章が載っておりとにかく読み応えがある。「私はただの良妻賢母に留まってはならない」という言葉通り、生涯勉強の手を止めずに日々を過ごす。一般的な幸福の追求ではなく、使命感を持って生きる神谷氏には尊敬と憧れの念を抱く。私の中で出会えてよかった作家の1人になることは間違いない。日記エッセイ好きなら読んで損はないだろう。2025/09/07