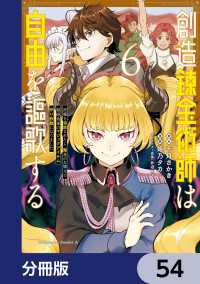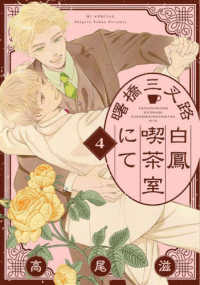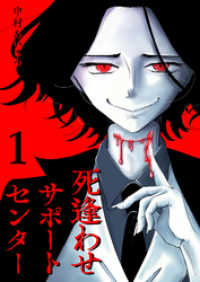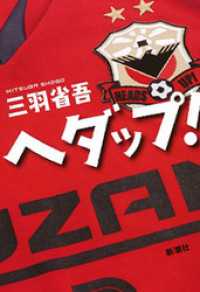内容説明
詩人・大岡信による名句・名歌アンソロジー。厳しい冬が終わり、伸びてくる日脚が春の訪れを告げている。春の到来の喜び、行く春を惜しむ心など古来より日本人は、移りゆく季節のなかで自然の輝きをとらえ、その心を凝縮した表現にこめてうたい続けてきた。本書では、万葉の時代から現代まで、古今の『春』の秀作を選び鑑賞する。春のエッセイ五編と「芭蕉について立派だと思うこと」を付載。
目次
春風
花
若草
雛祭
鶯
芭蕉について立派だと思うこと
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
12
四季のうちでも春のアンソロジーを編むのは大変な苦労が伴うだろう。どれを採ってどれを捨てるか。「かたまつて薄き光の菫かな」(渡辺水巴)近代写生句のひとつの頂だと思う。菫の花を珍重する私には放っておけない句。2020/03/07
ダイキ
2
「初めから自分自身だけの世界で完全に完結しているというものを目指すような人は、芭蕉的な世界あるいは日本の詩全体と言っていいですけど、そういう人は、日本の詩歌の世界では余り大した境地にまでは行かないということになります。不完全なるがゆえに無限なるものに向かって開かれているということを目指すのが、日本の詩だ、というように思います。」(芭蕉について立派だと思うこと)2019/04/15
彩美心
0
面白かった。句も歌もその解説もいいが、さいごの「芭蕉について立派だと思うこと」という文章もよかった。自己表現ではなく自己を無にして無限のものに開いていくという芭蕉の句作の仕方に感動した。そういう精神で私も俳句を作りたいと思う。2014/05/16
misui
0
「山もとの鳥の声より明けそめて花もむらむら色ぞみえ行く」(永福門院)、「ゆく春や蓬が中の人の骨」(榎本星布)、「梅散るや難波の夜の道具市」(建部巣兆)、「仕る手に笛もなし古雛(ふるひひな)」(松本たかし)2020/08/21
はしなぎ
0
最後の芭蕉についての文が良い。後書きの本を読むことの意識が書かれている文も中々ためになった。2020/01/05