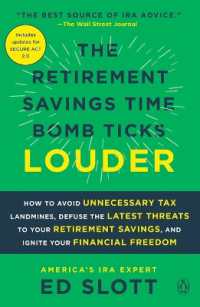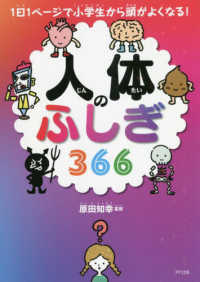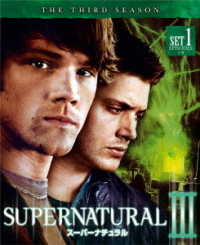出版社内容情報
梅原 猛[ウメハラ タケシ]
著・文・その他
柳田 聖山[ヤナギダ セイザン]
著・文・その他
内容説明
これまで禅は、禅問答や無の哲学に象徴される世界として語られてきた。本書は中国禅を中国仏教全体の流れにおいて捉え、禅を厳格に考える従来の解釈を排し、安楽に生きる知恵との関連から、斬新な禅思想を展開する。中国禅が生んだ『六祖壇経』や『臨済録』の禅語録のなかに、自由な仏性を輝かせる偉大な個性の記録を再発見し、「無の自由」を提唱する。
目次
第1部 禅思想の成立(ブッダの瞑想;道を楽しむ歌;奇跡の魅力;宴坐 ほか)
第2部 中国禅の特色―対談(柳田聖山;梅原猛)
第3部 絶対自由の哲学(厭世観の克服―『大乗起信論』;価値の世界を越えて―『六祖壇経』;深淵上の自由自在―『臨済録』;ユーモアと論理―『碧巌録』と『無門関』)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
井筒俊彦が禅仏教を存在論の哲学として語ったのは、坐禅が無分節の実在に触れる実践だからだった。本書はこの「無分節の実在」なる考えが老荘の混沌や道に由来し、中国禅を経て日本に渡来した経緯を辿る。インドの大乗において、全てを相互ネットワーク(縁起)とした「空」の思想は、中国禅で、分節された世界を生む無分節のエネルギーを表す「無」に翻訳される。インド仏教は、「空」を悟るために脱俗した。一方、凡夫にも仏性を見出す天台華厳を経て、その日常も肯定した中国禅は、根源としての「無」を仏教に導入し、仏性を全存在に充溢させる。2021/04/30
SE
3
中国における禅の発展を追う本。日本が中国哲学から甚大な影響を受けたことに気づかされる。インドにおける空の思想を老荘化して生まれた無の哲学や、日常生活の肯定にいたる禅哲学の展開をみると、日本のオリジナルと思われていた思想が実は中国由来だったというケースは相当多いのだろうなと思う。2018/11/27
マウンテンゴリラ
2
日本人にとって、念仏と並んで仏教の代名詞になっていると言っても過言ではない禅であるが、一面では分かり難さを象徴する言葉として捉えられ、逆説的に何かしら理解を拒絶するものが、崇高なものであると言う、一種の暗示に、私を含め現代人が心を惹かれる。つまり、凡人或いは修行の足りない人間には届かない、特別な真理がそこにはあるように感じてしまう。一方で、論理的に解釈する事を否定するかのような禅問答を象徴とする姿勢に、強い違和感も感じてしまう。という様に、憧れに似た敬意と、非現実的な議論への拒否感をないまぜにした→(2)2023/09/08
零水亭
1
筆者らは碧巌録、無門関などの公案メインの本よりも臨済録の「示衆」などの説法を重視しています。それはそれとして、禅の歴史から参考文献まで、「学問としての禅の入門書」として最適と思います(一方、「実際の坐禅の入門書」としては講談社学術文庫の大森曹玄『参禅入門』が最適でしょう)。2019/08/01
sikamo
1
概要説明かと思いきや思想史・成立史がメインだった。かなりの歯ごたえ。2013/07/18
-

- 電子書籍
- この本は僕の経験値を生んだ【タテヨミ】…