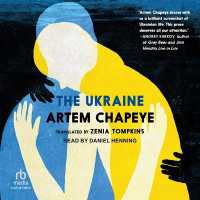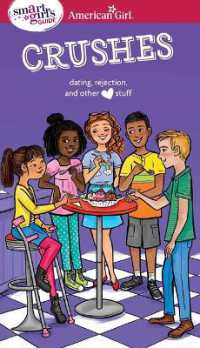出版社内容情報
千利休と対照をなし、”天下泰平の茶”を目指した稀代の大茶人・小堀遠州!
内容説明
戦国乱世を生き抜き、徳川の天下となったのちも、大名として、茶人として名を馳せた小堀遠州。おのれの茶を貫くために天下人に抗った千利休、古田織部とは異なり、泰平の茶を目指した遠州が辿り着いた“ひとの生きる道”とは。「白炭」「投頭巾」「泪」…茶道具にまつわる物語とともに明かされるのは、石田三成、伊達政宗、藤堂高虎など、戦国に生きた者たちによる権謀術数や、密やかな恋―。あたたかな感動が胸を打つ歴史小説。
著者等紹介
葉室麟[ハムロリン]
1951年、北九州市小倉生まれ。西南学院大学卒業後、地方紙記者などを経て、2005年、「乾山晩愁」で第29回歴史文学賞を受賞しデビュー。07年『銀漢の賦』で第14回松本清張賞を受賞し絶賛を浴びる。09年『いのちなりけり』と『秋月記』で、10年『花や散るらん』で、11年『恋しぐれ』で、それぞれ直木賞候補となり、12年『蜩ノ記』で第146回直木賞を受賞。16年『鬼神の如く黒田叛臣伝』で第20回司馬遼太郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐々陽太朗(K.Tsubota)
88
恥ずかしながら私は小堀政一(遠州)という人物をよく知りませんでした。山田芳裕氏が古田織部を描いた漫画『へうげもの』の登場人物として知っている程度です。 本書を読んで、「きれいさび」と言われる遠州の茶が少し分かった気がします。そして融通無碍ともいえる遠州の生き方に感銘を受けました。生き方でいえば、千利休が自分の求める美にこだわり豊臣秀吉から死を賜ったこと、同じく己の信じる美にこだわるへうげもの古田織部が徳川秀忠から死を賜ったことをを見れば、遠州の生き方はしなやかだと見える。2021/05/16
ふじさん
87
茶人として名を馳せた小堀遠州の人生を描いた作品。おのれの茶を貫くために天下人に抗った千利休、古田織部とは異なり、泰平の茶を目指した遠州。茶道具にまつわる物語と共に、明かされる徳川家康、藤堂高虎、石田三成、伊達政宗等、戦国時代を生きた人々の権謀術策が歴史の流れに沿って、遠州との関りで描かれ、面白かった。今まで、知らなかった歴史の裏側を垣間見ることも出来た。戦国時代を茶人として武将として生き抜いた彼の処世術は、司馬遼太郎が語っているように、すごい言わざるを得ない。こんな人物がいたとは、この本をおかげで知った。2025/09/23
のり
79
千利休・古田織部を師と仰ぎ、茶の道を邁進する「小堀遠州」。世の流れもあるが稀代の二人とはまた別の志で名だたる権力者を魅了する事に。政を左右するくらいの地位にもあたるが、遠州は泰平の世を願った。諸説はあるが利休も織部も我が強すぎた。激動の乱世を生き抜く者の術だったかも知れないが…世渡りといっては語弊がある遠州は名だたる者から心から信頼されていたと思う。2019/09/29
優希
57
しみじみとした作品でした。小堀遠州の生涯を描いた連作短編集。前々から庭に興味がありましたが、更に庭に興味を持ちました。2021/03/25
niisun
37
小堀遠州は大学時代に“庭園史”の授業で詳しく学びました。当時所属していた日本庭園研究会の京都合宿では、この作品にも登場する南禅寺の方丈庭園、金地院、桂離宮などをじっくりと巡りました。ただその頃覚えたのは名前と庭の特徴くらい。その後の出会いは漫画『へうげもの』。織部自刃までの時代ですが、作介(幼名)が個性豊かに描かれていて、私の中ではその印象で固まってしまいました。葉室麟版の小堀は、静かな佇まいを見せつつも、豪傑な武将達や老獪な公家衆相手に“生きるもののための茶”で見事に渡り合った好人物として描かれてます。2019/10/28
-
- 洋書
- The Ukraine