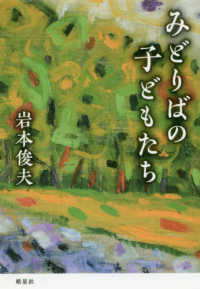内容説明
島津斉彬の死後、藩命により潜居していた大島(奄美)で、砂糖専売などの薩摩藩による苛政を目の当たりにした西郷隆盛。改革に取り組む西郷は、島人から指導者として慕われるようになり、やがて愛加那という妻をめとる。そのころ薩摩藩は八月十八日の政変により京都政界での発言力を高める一方で、有能な人材が払底していた。窮地を打開するため同志らの働きかけで西郷は召還され、幕末の動乱に身を投じていくが―。
著者等紹介
海音寺潮五郎[カイオンジチョウゴロウ]
1901(明治34)年、鹿児島県生まれ。國學院大學卒。教員生活の後、創作に専念。36年、『天正女合戦』『武道伝来記』で第3回直木賞を受賞。77年12月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おにく
28
これまでは出身地の絡みで、主に会津藩や新撰組の視点で幕末を見る事が多かったのですが、そもそもの発端はペリー来航後、列強国ひしめく国際社会と、どう渡り合うかが急務となる中、弱腰、逃げ腰、隠蔽体質の幕府では諸外国に不利な条約を結ばれ植民地化されてしまう。これに業を煮やした若い志士たちが幕府を倒そうと暗躍する。この流れは薩摩藩を中心に据えるとよく分かりますね。西郷さんや大久保らは、藩主の島津久光とは思想が違う中、これまた水と油のような長州と手を組もうと奔走。この頃の西郷さんは人間的魅力に溢れていますね。 2018/01/27
フミ
24
西郷隆盛の小説…ではなく、薩摩藩から見た幕末史といった感の情報密度の濃ゆい伝記、2巻目です。1巻目と比べて、前半が読み易いな…と思ったら、寺田屋事件前後や、島流し中の話だったり。中盤以降、特に「第1次長州征伐」での外交交渉を務める辺りになると、緻密さがぐっと上がって難解に。かなり流して読んだ感じですが、西郷さんの「精神の安定感」は凄いですね。2月に島流し解除→11月、12月には連合軍の偉いさん(ご家老級)相手に、堂々と弁舌を振るう~とか、10か月ほどで、これだけ立場が変わって、精神不安定にならないという。2025/04/05
kouichi
14
西郷を始めとする青年らが、日本のために命を懸けて行動していく様子に、大変に感銘を受けました。現代ではなかなか考えられないなと思いました。ただ、現代でも、少なくとも、“後に続く子供たちのために、この日本をどうするのか” というような視点は持たなくてはダメだなと感じました。2018/04/27
BIN
11
薩長同盟・第二次征長前まで。第一次征長の時点で長州が滅ぼされないようにと西郷さんが動いていたとは知らなかった。島津久光は西郷さんを嫌いまくってる。声望のある西郷を使わざるおえなけど、声望高まるのは嫌だからと邪魔をする。藩主でもないのになとちょっと思ったりもする。それにしても幕府の杜撰さ・無能さは憐れ。小栗とか勝みたいな有能な人物いても頭が腐っていたらどうしようもないですね。私は佐幕びいきなので薩長陣は比較的嫌いな方ですが、これを読んでいたら幕府倒れてよかったねと思ってくる。2018/04/14
タカボー
7
ストーリーの大半は長州征伐。この巻は西郷が何をしたのか、人となりもよく出てて、わかりやすくて、スイスイ読めた。なぜ下級藩士の西郷や大久保がこんなに出世して、こんなに大事な役ができたのかな?って思ってたけど、家老の小松帯刀の存在、大きいなって思った。会社で考えても、社長に直接意見言うのは部長クラスだから、随分風通しの良い藩だとは思う。上の世代は何してるの?って気にはなる。2020/08/11