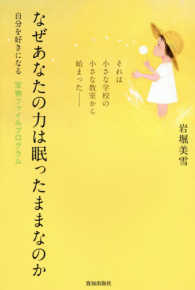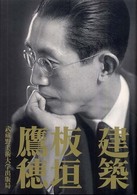- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
目次
未来を予測することは可能か?
イノベーションを予測することはできない
人間にはストーリーが必要だ
権威システムvs.検証システム
ビッグデータの本当の意味
人工知能の可能性
コンピューティングパワーがすべてを制する?
ネットの巨人達が国家に取って代わる
超巨大企業を所有してしまえばいい
経済発展はこれからも可能なのか?
比較不能な「差」を見つけよ
人間は何が欲しいのかを知らない
欲求こそが希少な資源である
機械が欲求も持つようになる?
どうすれば好奇心が伸びるのか
文系は不要か?
反知性主義と科学的リテラシー
格差問題をどう乗り越えるか
著者等紹介
神永正博[カミナガマサヒロ]
東北学院大学教授。1967年、東京都生まれ。京都大学大学院理学研究科数学専攻博士課程中退。博士(理学)。2010年度はThe Institute of Mathematical Sciences客員研究員として南インド(チェンナイ)に滞在
小飼弾[コガイダン]
投資家、プログラマー、ブロガー。1969年、東京都生まれ。中卒後、大検で高卒資格を取得。カリフォルニア大学バークレー校中退。株式会社エン・ザ・エッヂ(後のライブドア、現在の株式会社データホテル)の取締役最高技術責任者(CTO)を務め、同社の上場に貢献。現在、ディーエイエヌ有限会社代表取締役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
28
与えるデータと推論のアルゴリズムによって、人工知能格が出てくる。解決しなければならない問題も違うので人工知能が活躍する社会は楽しいと思う。ただ、今人工知能で解こうとしている問題は、あくまでも研究者自身の欲求の範囲内に収まっている。人工知能自身が欲求を持って、自分が解くべき問題を見つけて解くところまでは到達していないGoogleのコンピュータはまるで知性があるかのように私たちの質問に答えてくれるから、生きているように見えるけれど、我々の欲求に依存しているという意味で、まだ生命には至らない「半生命」と言える。2019/11/24
maito/まいと
13
よく将来に関する予測が様々な切り口で報道されているけど、これアテになるの?というぶっちゃけた疑問に対して、著者二人が対談形式で好き勝手いう1冊。身もふたも無い結論で巷の雰囲気をバッサリ切り捨て、未来については見方を変える必要があることを提言している。確かに専門家が予想した未来をなぞる(に沿った)生き方をする必要は無い、という論調には大賛成。少し先はともかく遠い未来はもはや予想できる範疇を超えていると割り切り、未来を創る側へ自分を移した方がおもしろそうだ。2015/09/08
nizimasu
5
久々に小飼節が読めたのは痛快。いつものベーシックインカムの話はどうでもいいのですがw、未来は予測出来るのかというテーマがいきなり逸脱。予測はできないというよりも統計のウソの話になり思考のフレームワークへとつながっていく。実は我々が考えるフレームワークはストーリーでありそれがあたかも万能なようにみえるものこそ怪しいと論破する。未来予測も同様でフレームワークの中に収めようとするとはみ出していくという結論は納得。そこから予測には精度をあげるための検証システムが必要でありというのがなかなか難解でしたが楽しい対談集2016/06/30
Kentaro
3
世の中をもっと先に進めるという上で、これから必要なのは自分がバカかもしれないということをきちんと認め、自分にはここが分からないからこの部分は専門家に委ねようと考えるリテラシーを持つことである。 リテラシーとは自分が何を知らないかを知るための学びである。分かったふりをして進めてはほぼ成功するには至らないでしょう。 そして、学びを通して好奇心をもって仕事を進めるのです。リテラシーがなく、一見従順に見える人間の仕事は、きっとロボットに置き換わっていくことでしょう。2018/05/17
まゆまゆ
3
未来が予測できるのか、という問いに対しては、決まっていることは多いが、わからないことの方が多いというもの。社会現象を予測することは難しい。そもそも人は何を欲しているのかを科学的に立証できないので、理由は必ず後付けである。疑うことにはコストがかかるため、無意識に完成された権威システムによって判断している、との指摘はなるほどと思う。2015/03/02