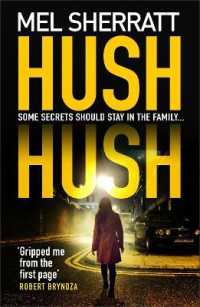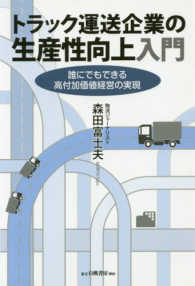内容説明
旅にでたセレンディップ(いまのスリランカ)の三王子はベーラムの国でかけられたラクダどろぼうのうたがいをずばぬけた機転によって晴らし、皇帝の命をもすくう。皇帝の信頼をえた三人は、うばわれたベーラムの宝「正義の鏡」をとりもどすため、インドへむけてふたたび旅にでた―十八世紀の英作家ウォルポールが読み「セレンディピティ」ということばを生むきっかけとなった物語。小学上級から。
著者等紹介
竹内慶夫[タケウチヨシオ]
1924年東京に生まれる。東京大学大学院特別研究生中退、マサチューセッツ工科大学研究員。東京大学教授を経て日本大学文理学部教授。日本鉱物学会会長、日本結晶学会会長を歴任。現在は東京大学名誉教授。理学博士。専門は結晶学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- これから幸せになります! 虐げられ令嬢…
-
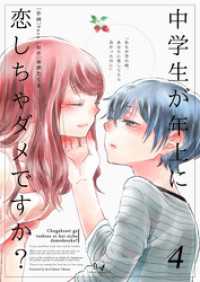
- 電子書籍
- 中学生が年上に恋しちゃダメですか?4巻…