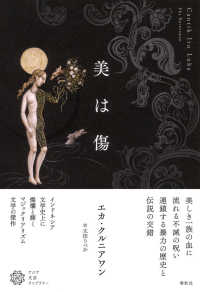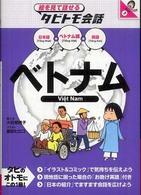出版社内容情報
民意とは何か。国民民主党の躍進はSNSによるものなのか。80年代の中曽根政権、2000年代の小泉政権、安倍政権での「民意」を軸に、各党の世論調査や情勢分析のほか、参政党、日本保守党も含めた動向を分析。派閥・中間団体が消滅した現代日本の権力奪取の構図を独自取材で追う。
内容説明
各政党は「民意」をどう分析しているのか?最新の世論調査と情勢調査で見るリアル・ポリティクス 大衆社会における個人の「原子化(アトム化)」が進む今、政治の世界、とりわけ選挙では、短い言葉でメリハリの利いたことを言った方が「勝ち」となる。たとえそれが、実現不可能であったとしても、だ。ポピュリズム(大衆迎合主義)によって民意をまとめる手法は危ういが、SNSによる虚実ないまぜの膨大な情報は、選挙のあり方を変えている。派閥・中間団体が消滅し、ポピュリズム的傾向を強める現代日本の政治状況を、独自取材で追ったノンフィクション。
目次
序章 民意とは何か―現在に続く中曽根康弘の嘆き
第1章 SNSと動画サイト―2024年の選挙を振り返る
第2章 世論調査と情勢調査―マスコミと政党はどのように選挙分析しているか
第3章 中間団体の衰退とポピュリズム―SNS民主主義の危険性を考える
第4章 岩盤支持層と分断的手法―55年体制以降の「人気取り」の変遷
第5章 派閥を解消した自民党―一気に力を失う「大物」たち
第6章 「砂の民意」のもとで進む多党化―参政党の「オーガニック信仰」と神社崇拝etc.
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
29
80年代の中曽根政権、00年代の小泉政権、安倍政権での民意を軸に、各党の世論調査や情勢分析、参政党や日本保守党も含めた動向を分析した1冊。民意とは何か。国民民主党の躍進はSNSによるものなのか。SNSと動画サイトが注目を集めた24年の選挙を振り返りながら、マスコミと政党はどのように選挙分析しているか、中間団体の衰退とマスコミ不信によるポピュリズムの台頭、55年体制以降の人気取りの変遷から、自民党が派閥を解消した影響、与野党トップが中道路線という状況で、政権交代ではなく多党化へ向かう解説は興味深かったです。2025/07/05
どら猫さとっち
20
ちょうど、参院選が近いときに読み始めた。SNSや動画サイトを駆使した選挙が、昨年かつてない結果を生み出した。しかし、それは恐ろしい事態を引き起こすことにつながった。私たちの民意は、SNSや動画サイトで反映されているのだろうか。かつて中曽根康弘がいう、粘土が砂になった時代、ポピュリズムによる大衆民主主義はどこに向うのか?これからの政治を知るうえで、本書はひとつの手がかりになるだろう。2025/07/20
かず
14
政治学のレポート記述のため読書。課題はメディアと政治の関係性について述べ、インターネットがどう影響するかというもの。今や新聞、TVはオールドメディアと呼ばれ、敵視されている。その代わりのSNSであるが、功罪両面の意見が掲載されている。私はSNSの負の作用を実感している。左右両方の新聞社のFacebookを閲覧するが、コメント欄は率直にいっておぞましい。そこにフェイクニュースが入り込む。今後エスカレートしていくだろう。政治とは一般意思を実現するもの。市民の良識を望む。沈黙の螺旋の逆パターンが興味深かった。2025/11/27
バーバラ
8
看板に偽りあり。政治活動とりわけ選挙戦に蔓延るデマやポピュリズム批判を展開するのかと思いきや朝日お得意の政局絡みの内容が多くを占めて白けた気持ちで読み終えた。維新議員のマーケティングのような戦略の件も批判的視点がなくつまらなかった。本書が書かれたのは石破政権時代で終盤は高市政権圧勝の総選挙後に読んだからタイミングも悪かったかな。朝日新書は少し前に社会部が骨太のルポを出版してこちらは読み応え充分だったけど、本書は期待外れが否めない。2026/02/10
みじんこ
8
中曽根康弘の民意を砂と粘土に例えた話から始まり、2024年のSNSが活用された選挙を振り返ることで現代日本の政治状況が見えてきた。逆「沈黙のらせん」効果等、様々な引用がなされ情報量が多い。選挙でSNSやデータ分析を活用している政治家の実例も紹介され、戦略としては正しいのだろうが憲法43条の「全国民を代表」するという建前を踏まえると悩ましい。終盤で参政党について触れられているが、中間団体の衰退等これまでの論考と「細分化された民意」の反映も相まって伸長は必然だったのだと思えた。刊行当時より更に混沌としている。2025/10/19
-
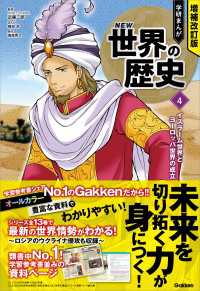
- 電子書籍
- 増補改訂版 学研まんが NEW世界の歴…