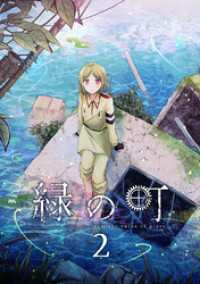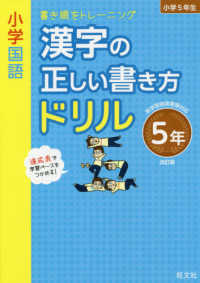出版社内容情報
2040年に1200万人の労働力が足りなくなる。迫り来る超人口減少社会とどう向き合うか。取材班が現場を歩き実態に迫り打開策を探る、「朝日新聞」大反響連載を書籍化。多和田葉子氏、小熊英二氏、安宅和人氏、増田寛也氏ほか識者インタビューも収録。
内容説明
止まらぬ少子高齢化―。現役世代が2割減る“不都合な未来”は変えられるのか?様々な業界で「人手が足りない」と悲鳴が上がっている。生活を支えるインフラやサービスの担い手がいなくなり、社会が立ち行かなくなる現実味が増す今、私たちはこの難局にどう立ち向かえばよいのか。各地の実態に肉薄し、現状打破に奮闘する人々を描いた、「朝日新聞」大好評連載の書籍化。
目次
第1部 現場から(縮小の先に;人手奪い合い;変えられた未来;切り札はあるか;適応できるか;発想を変える;主役世代;突破への胎動)
第2部 ともに支える(若い世代と考える;ロスジェネ女性の道筋は;政治家に聞く「解決の鍵」;世代間不公平を考える―世論調査から)
第3部 能登半島地震―震災からみえたもの(被災地の現実;地方自公体の模索;過疎集落はどうなる;災害と人口移動―データから読み解く;防災と復興―識者はこう考える)