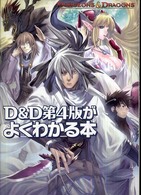内容説明
一七世紀に中国で発見され、西洋に伝わった紅茶は現在一二〇カ国以上にもわたり、人々の生活に溶け込んでいる。紅茶で戦争が起こり、植民地が作られた。おいしさの論争も起こった。そして今、時代の流れとともに伝統も変わりつつある。紅茶の歴史と未来、魅力に迫る。
目次
第1章 世界中で愛されてきた紅茶
第2章 変化する紅茶の世界
第3章 紅茶のおいしさとは何か
第4章 紅茶への期待
第5章 未来の紅茶
コラム 茶葉を知る―材料としての紅茶
著者等紹介
磯淵猛[イソブチタケシ]
1951年愛媛県生まれ。紅茶研究家・エッセイスト。青山学院大学卒業後、商社勤務を経て、1979年紅茶専門店ディンブラを開業。紅茶の輸入、レシピの開発、技術指導、経営アドバイスなど紅茶研究の分野で幅広く活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





COSMOS本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ロッキーのパパ
16
紅茶についての基礎知識がコンパクトにまとまっている。ただ、惜しむらくはうんちく本にとどまっている。紅茶の魅力を伝えようとしているんだけど、紅茶を飲まない人を引き付けるところまで行っていない気がする。ただ、「ワインはセレクションで決まり、紅茶はメイクで決まる」という言葉は印象的だった。紅茶はストレートが好きでそれ自体の味を楽しむことが多いけど、料理やお菓子とのマリアージュも考えてみようかな。2012/04/10
澤水月
14
イギリスでは料理が苦手だから簡単な茶菓に合う紅茶が発達した説に噴く。紅茶マニアがあちこち話飛ばしつつ書いたようなサラリ感(他に深い著書があるようだ)、カテキンやカフェイン効用説くほど珈琲、日本茶とも重なるよなぁと…でも読んで紅茶を多く飲むようになりました。12年刊本書で夢とされるコーヒーメーカーのように施設に設置できる茶葉からのティーメーカーはいまだにないなぁ2019/03/06
月世界旅行したい
12
わりと現代の話もある、歴史だけではない内容。2015/09/21
Humbaba
12
紅茶は,産地によって味が大きく違う.どれが良いかというのは好みによっても異なるため,一概にこれを薦めることはできない.その違いを味わい,自分はおdのようなものが好みであるのかを認識することは,これからのお茶をより一層楽しむために役立つであろう.2012/02/11
m
4
身近だが実はよく知らない紅茶の奥深い話。陸路から伝わった茶はCHA、海路から運び込まれたものはTEAと伝播経路によって名前が異なるのが面白い。茶葉の種類や飲む温度によって合う料理が違ったり、ミルクティーでもミルクを先に入れるか後に入れるかで風味が変わるとか。最近暑くて麦茶ばかり飲んでいたが、これを機に紅茶を深めようかな。2020/09/02
-

- 電子書籍
- 医療ソーシャルワーカーのスーパービジョ…
-

- 電子書籍
- 婚約破棄された捨てられ令嬢ですが、触れ…
-
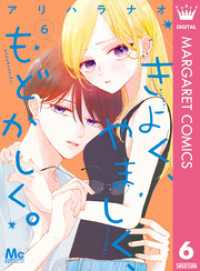
- 電子書籍
- きよく、やましく、もどかしく。 6 マ…
-
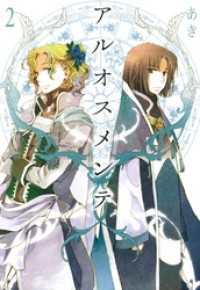
- 電子書籍
- アルオスメンテ: 2 ZERO-SUM…