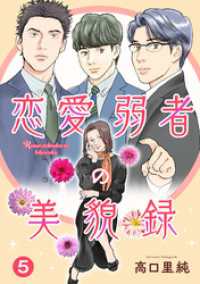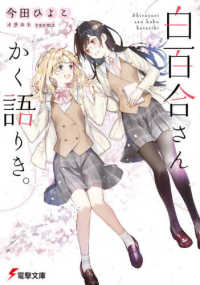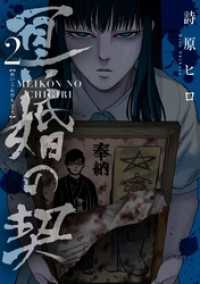内容説明
「帝国」の栄枯盛衰を見つめたシルクロード。その有為転変と人びとの「運命」をイスラムと国際政治に通じた筆者が綴る。司馬遼太郎、カフカ、松本清張は、この路に何を仮託し、島津斉彬とムハンマド・アリー、東西の傑物は何を残したか。東西の歴史をつなぐシルクロードに埋もれる逸話の数々、いま、世界史と日本史の像がいきいきと結びつく。
目次
第1部 歴史と文学をつなぐシルクロード(司馬遼太郎とカフカ;シルクロードのノーベル賞作家―パムクとイスラーム史 ほか)
第2部 シルクロード古今抄(苦悩する現代のシルクロード;トルコとアルメニアの和解は可能か ほか)
第3部 日本史とシルクロード異聞(斉明天皇と「麻薬の酒」―『火の路』としてのシルクロード;オスマン宮廷料理と徳川将軍の台所 ほか)
おわりに アジアゲートウェイの未来に向けて
著者等紹介
山内昌之[ヤマウチマサユキ]
1947年生まれ。北海道大学文学部卒。学術博士(東大)。カイロ大学客員助教授。ハーバード大学客員研究員などを経て、現・東京大学教授。2002年司馬遼太郎賞受賞、06年紫綬褒章受章。著書に『現代のイスラム』(発展途上国研究奨励賞)、『スルタンガリエフの夢』(サントリー学芸賞)、『瀕死のリヴァイアサン』(毎日出版文化賞)、『ラディカル・ヒストリー』(吉野作造賞)、『岩波イスラーム辞典』(編著、毎日出版文化賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
13
図書館本。私がいつも好んで読むシルクロードとはまた違った角度から綴られている。各地の文学や現代のシルクロード各国の現状を紹介したり、日本、あるいは西洋との比較などもあり、これからのシルクロードを考える上で興味深い。中国の掲げる「一帯一路」はシルクロードが過去のものではなく現代も生きている道なのだと実感する。この本で紹介されている司馬遼太郎『蒙古桜』、オルハン・パムク『わたしの名は紅』、松本清張『火の路』読んでみたい。2019/05/13
スプリント
7
地理や交易だけでなく、各地の文学を軸とした文化に焦点をあてていることが新鮮でした。2019/03/30
ようはん
5
シルクロードにまつわる様々なエピソードをエッセイとして紹介。文学を含め著者の教養の幅広さと深さが強く感じられ羨ましい。2019/10/17
こにいせ
4
イスラームと日本を中心にした歴史語り調エッセイ。おしなべて評価がよろしくないようだが、この本を低く見積もる方々は、著者と同じだけの広範な知識・教養をお持ちの上に、新聞に連載出来るだけの誰から見ても無駄のない整った文章を当然のように書けるような、素晴らしい頭脳をお持ちなのだろうな。本を出すのがよろしかろう。それに比べて私は頭が本当に悪いので、本書のような歴史を好きになれる、わざと敷居を低くしている本に出会うと、心から感動してしまうのである。2010/04/18
鳥羽
2
エッセイ集だが、古今東西の広範な知識が詰め込まれている。見慣れぬ語彙が多く、読むのに少々苦労したが、内容が面白いので退屈はしなかった。2016/05/10