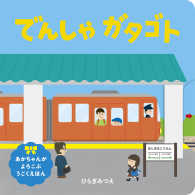内容説明
鋭い批評精神とやわらかいユーモアの光る、傑作随筆全七四編。講談社エッセイ賞受賞作品。
目次
たしか
会っていた
道
本を見る
畑のことば
芥川龍之介の外出
社会勉強
色
秩父
読書のようす〔ほか〕
著者等紹介
荒川洋治[アラカワヨウジ]
1949年福井県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1976年、『水駅』で第26回H氏賞を受賞し、詩壇に登場。1996年より肩書を「現代詩作家」とする。『渡世』(1997)で第28回高見順賞、『空中の茱〓(ぐみ)』(1999)で第51回読売文学賞、『心理』(2005)で第13回萩原朔太郎賞を受賞。エッセイ・評論も多く、『忘れられる過去』(2003)で第20回講談社エッセイ賞、『文芸時評という感想』(2005)で第5回小林秀雄賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Rin
43
自分の感じたことを表現しようとする時に上手く表すための言葉をきちんと知っておきたいと痛感した。本を読む人、を表すだけでも「趣味が読書、本好き、読書家、読書人、蔵書家、愛書家」とたくさん出てくる。読書を通じて言葉を正しく知って、ていねいに使いたい。そして、本は読むだけじゃない、眺めてなぞって、何を読もうか?と考えることも読書のうちだと。読まない、読めない本が存在することが読書を失わないこと。その言葉が嬉しかった。漢字の使い分けや詩について知ることが出来たし、荒川さんの本への向き合い方がとっても素敵でした。2016/03/13
あんこ
33
なんとなく手に取ったら、解説にカワカミさん。そんなこんなで読んだのですが、とてもよかったです。「ていねい」に生きる、という意味がしみじみわかりました。読書(再読)に関する『会っていた』に共感し、芥川龍之介の外出をもとに、いまのように簡単に連絡がつくわけではなかった時代の人々の来訪に思いを馳せた章にはなるほどと思いつつ、感動すらおぼえました。硬すぎず、柔らかすぎず、ほどよい雰囲気を醸し出しているエッセイでした。「ていねい」にいきたいものです。2015/01/23
kana
31
荒川洋治という現代詩作家であり、文芸評論家であり、エッセイストである彼を私は全く知らなかったのですが、本屋で冒頭の「会っていた」を読み、引き寄せられるように購入。時々こういう電撃的な出逢いがあり、今回もその出逢いの貴さを噛み締めるように読む。平易な言葉を組み合わせて、研ぎすまされた美しい文章を創り、宇宙のような言葉の広がりの可能性を感じさせてくれる74篇。テーマも読書や言葉についての普段、着目しないけれど大切なこと、と思われるものばかりで、とても好みでした。2012/01/29
Yusuke Oga
13
名言連発。「身動きできない。社会も何も、こちらの思うようにならない。それでも人は自分が支配できるものがあることを望む。その点ことばはいい。知識としてのことばは死体(または記号)だから好きなことができる。きりきざまれようと、もてあそばれようと、ことばには口がないから、抵抗もできないし文句のひとつもいえない。ことばブームは「弱いものいじめ」なのだ。」こういうことをいつでもさらりと喝破してのけるから恐れ入る。荒川さんの本は誰でもが読めるほど易しく綴られているが、見た事もない地平に(ふらふらと)連れていかれる。2014/06/26
Yuki Ban
11
読んだことあるな〜と1/4くらい思いながら読了。2年半前に読んでました。当時はあんま入ってこなかったらしいけどまた読みます絶対と記録してあった。叶えたよ〜。当時より入ってくる率は上がった気がする。解説の川上弘美さんの指摘した、荒川洋治さんのていねいさを上げられてよかった。また読も。2022/05/11