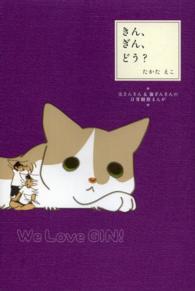内容説明
文学は、私たちの「いま」を映す鏡である。太宰治『斜陽』から、三田誠広『僕って何』まで、「自己」と「性」というテーマを浮かびあがらせる10篇を通して、近代文学から現代文学への変容を捉える、新たな読みの試み。
目次
第1章 もう一つの、敗北を抱きしめて―太宰治『斜陽』
第2章 「作者」になるための物語―三島由紀夫『仮面の告白』
第3章 「恋」を知らない恋人たち―大岡昇平『武蔵野夫人』
第4章 「僕ら」とは誰か―大江健三郎『芽むしり仔撃ち』
第5章 裏返された家族―安岡章太郎『海辺の光景』
第6章 二つの身体―安部公房『砂の女』
第7章 主婦になり損なった男―小島信夫『抱擁家族』
第8章 「あなた」の向こう側―倉橋由美子『パルタイ』
第9章 地図のない女―古井由吉『杳子』
第10章 アイデンティティはもう古い?―三田誠広『僕って何』
著者等紹介
石原千秋[イシハラチアキ]
1955年東京都生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専門は日本近代文学。現代思想とテクスト分析による斬新な読みを提示すると同時に、国語教育の指南者としても注目されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
53
戦後日本小説の評論。主にテキストから分析していく。取り上げられた10編は名作ばかりだ。正直自分には肩透かしな論があったがトリビア的な知識がなかなか面白い。『男友だちが「マグロの刺し身」を買ったと聞いても「そうなの」で終わりだ。しかし、彼が「彼が男を買った」と聞いたら「エッ!」となるだろう。近代は、性的な言説がその人の真実を語るディスクールとなった時代である。近代は「性的な言説」が「真実の言説」を構成した時代だ。だからこそ、それは内面深くに隠すべきものになり、逆に「告白」するに値する情報=真実となる。』2016/09/27
ハチアカデミー
13
いまでも書店で買うことができる文庫本の中から10作品を取り上げ、現代の教養としてどのように読めるのか、読むべきなのかをレクチャー。時代を超えてテクストを結びつける。ダワーの『敗北を抱きしめて』と『斜陽』、中沢新一『アースダイバー』と『武蔵野夫人』などなど、読みの可能性を堪能。主語をめぐる大江・倉橋論、卒論が安部公房(しかも『砂の女』)だった人間には耳が痛い第六章などが印象に残る。本書をツールとしてみれば、何よりも巻末の参考文献が一番訳に立つ。膨大な読書の中から、本書を書くために選ばれた名著が並ぶ。2014/03/28
いっち
5
作品にまつわる作者のエピソードが冒頭にあり、作品の読み解き方を綴る。一人称の視点のずれなど、テクスト論から解説するので、普段自分が読んでいる読み方とは全く違い、新鮮であった。それだけに面白くはあったが、難しかった。解説本よりも元の作品を手に取りたくなった。「わたしがわたしでありうるためには、わたしは他者の世界のなかに一つの確かな場所や占めているのでなければならない」承認欲求はいつでも。2016/03/15
ワンタン
3
自分の好きな古井由吉の『杳子』を取り上げた章だけ拾い読み。石原千秋の本は漱石についての評論をちょっと読んだことがあるだけだったが、今回読んでみて、引用している文献も含めて非常に面白かった。ヒロインである杳子だけでなく語り手である男も含めた、物語の中の視点・視線の分析が、そういう見方もあるのか、と新鮮な思いで読むことができた。ただ、結論がけっこう断定的で、あっ、もうお終い?とちょっと驚く(自分にとってはドキッとする結論だった)。もう少し詳しく分析してほしかったが、入門書の中の一章だから仕方ないですね。2016/10/08
void
2
【★★★★☆】「小説の神は細部に宿る」。その細部に対する感度が高い。ざっくり言うとアイデンティティや他者論、家族、個と社会などに整理されてしまうのだけど、しっかり「細部」から立ち上げていることに圧倒される。2014/07/05