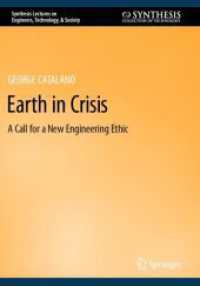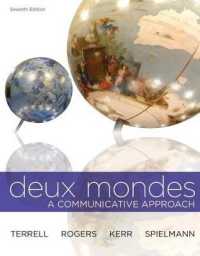出版社内容情報
神戸製鋼、希望の党、日本相撲協会、大学改革など、よかれと企図した組織の改革が頓挫するのはなぜか? 改善を図ろうとした改革が改悪へと合理的に変化していく様を分析し、「改革の不条理」を超えていくための方法を明らかにする。
内容説明
相撲協会、希望の党、神戸製鋼、大学改革―。よかれと企図されたはずの「改革」は、なぜ次々と失敗してしまうのか?改善を図ろうとした改革が改悪へと合理的に変化していく様子を理論的に分析。4つの「改革できない理由」をもとに、「改革の不条理」を回避する方法を解説する。
目次
第1章 「改革できない理由」は4つある
第2章 「改革の対象」とは何か
第3章 「改革策」に潜む不条理
第4章 「改悪」に導く不条理
第5章 「改革の主役」は誰か
第6章 「改革の不条理」を超えて
著者等紹介
菊澤研宗[キクザワケンシュウ]
1957年石川県生まれ。慶應義塾大学商学部・大学院商学研究科教授(商学博士)。慶應義塾大学商学部を卒業後、同大学院博士課程を修了。防衛大学校教授・中央大学教授などを経て現職。その間、ニューヨーク大学スターン経営大学院やカリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院で客員研究員として研究を行う。元経営哲学学会会長(現理事)、日本経営学会理事および経営行動研究会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
25
組織の不条理より10年後に出版。内容もほぼ同じだが、エージェント理論や心理会計、リーダーシップについてなど、扱う幅がさらに広く、図表も載っていてわかりやすい。終わりにのところには、あくまで経済的なアプローチで一面的な見方であることに留意しつつ、その深めた一面から他方面からの見方も養ってほしいという著者の思いが綴られており、共感した。自分の仕事に思い当たることが多々あるので、実際に応用したいと思う。良書。2019/01/20
さきん
24
組織の不条理の続編で、10年後に読みやすい形で出版。内容は組織の不条理とほぼ重なるが、エージェント理論や心理会計の話など図表を使った解説も増えてわかりやすい。自分の仕事でも、思い当たることばかりなので、何回も読み直して、現実社会に応用していきたい。2019/01/20
nishiyan
17
前作である『組織の不条理ー日本軍の失敗に学ぶ』では取引コスト理論、エージェント理論、所有権理論用いて組織の失敗を分析していた。本作ではそこにプロスペクト理論(行動経済学)を加えて、豊富な事例を元に「改革はどうして失敗する(した)のか」を分析している。山本七平氏が「空気」と呼んだものが、一つ一つ説明されていくところは痛快でもある。改革を改悪に、改善のための取り組みを挫折させないためにはどうすべきかいろいろと考えさせられた。2018/05/21
ふぇるけん
13
行動経済学視点で、なぜ組織改革が「合理的に失敗」するかを解説。信望の厚いリーダーほど改革に失敗する(説得に膨大が取引コストが必要)、「空気」とは取引コストが生み出す沈黙、意味のない会議が開かれるのはプロジェクトを形式的に共有することで所有権をあいまいにすること、など現実の組織で起こっていることのメカニズムが一側面とはいえクリアに説明できている。こういった不条理を避けるためには、リーダーやメンバーが自身の限定合理性を認識し、批判的議論を展開し、絶えず変わり続ける組織を形成することが必要だ。2018/06/01
coldsurgeon
9
様々な社会の中の組織で、改革というのがうまく進まず、また改善どころか改悪なったり、とん挫するのは、何故かを、論じたもの。最新の経営理論を、比較的わかりやす、直近の事例を示して解説。改善を追行するためには、開始時の強い決意が必要なため、人情味や人気があるリーダーではだめであり、「空気に水を差すこと」ができるある意味非常なリーダーが要求される。そして、制度的に改善を図るだけではだめであり、個人の誠実さ、損得計算を超えた誠実さが必要である。なかなか難しい議論があるが、読んでよかった。2018/06/21