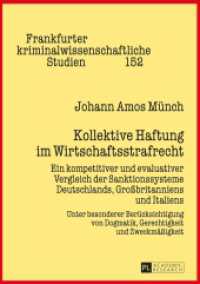内容説明
アマゾンジャパンの物流倉庫に、ひとりのジャーナリストが潜入する。厳しいノルマとコンピュータによる徹底的な管理。そしてアマゾン社員を頂点とする「カースト制度」のなか、著者が目にした「あるもの」とは…。驚異的な成長の裏に隠された真実に迫る。
目次
第1部 アマゾン・ドット・コム潜入(密かに急成長するアマゾンジャパン;アマゾン・ドット・コム上陸前夜;アマゾン心臓部・物流センターの実態;空虚な職場に集う人々;アマゾンの秘密主義を恐れる出版業界;日本で躍進した本当の理由;その強さの裏側にある底辺;アマゾンの目指す「完成形」)
第2部 その後のアマゾン・ドット・コム(ブックオフとの関係とアマゾンの変化;マーケットプレイス潜入;電子書籍端末「キンドル」は出版を変えるか)
著者等紹介
横田増生[ヨコタマスオ]
1965年福岡県生まれ。関西学院大学を卒業後、予備校講師を経て、米・アイオワ大学大学院に留学。ジャーナリズム学部を卒業。93年に帰国後、物流業界紙で編集長を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
hatayan
41
2010年刊。Amazonの流通倉庫に単身潜入、秘密主義を徹底する現場の様子をレポート。1970年代の名著『自動車絶望工場』を引きながら、トヨタにあった希望がAmazonにはないと対比します。 目利きの機能を書店員からコンピュータにいち早く肩代わりさせ、新刊と中古本を同じサイトで売ることを躊躇しなかったAmazon。今や市場を支配するプラットフォームとなり、巨大IT企業集団「GAFA」の一角として君臨しているのは承知のとおり。 単行本は2005年刊。現在を不気味にも予言した書としても読めそうです。2019/07/01
らむり
39
なかなか面白かったけど、顧客第一主義の実体を知って、アマゾンのイメージ最悪だわ。使い捨て労働者、地主と小作人の関係…。それでも利用してしまう、便利なアマゾン。。2014/07/18
mazda
21
横田さんの潜入第一弾。この時は小田原ではなく、市川塩浜のFCへの潜入です。アングロサクソンの考える商売方法というのは、骨の髄まで労働者から搾取することなんだな、と改めてその末恐ろしさを感じた次第です。1分3冊ピックアップがノルマのピッキング作業、2カ月ごとの契約更新で、社会保険も年金も一切関係なし。仕事を休めばポイントが減り、あるところまでいくと強制排除。地球上で最もお客様を大切にする企業に嘘はない代わりに、労働者をとことんまで追い込みます。躍進する会社だけに、注目されてしまいます。2019/10/28
ででちゃん
21
物流関係筋との商売での関わりは色々あると思うが、アルバイトを介在した話しは興味深く読んだ。 某自動車メーカーとアマゾンとの働かせ方の違いについての考察は納得だ。 何もかもが、効率、利益重視で推移していく環境はこれからも拡大していくのだろう。 この筆者も書いているがアマゾンが顧客満足に力をいれているのは実感として分かる。 巷の書店の足りない部分を補ってあまりあるネット書店であり、実際、便利で重宝している。 ただ、その利便性、快適さを支えている現場の人達に少なからぬ想いを馳せた。2014/10/10
しーふぉ
17
Amazonはアルバイトやマーケットプレイスへ出品する人から搾取して成長しているとの主張。ブックオフで仕入れてAmazonで売る。現在のセドリが面白かった。月収40万か〜2016/02/08
-

- 和書
- 刑法基礎理論の可能性