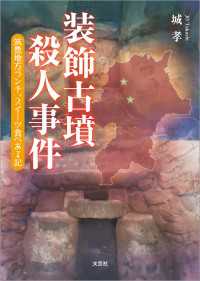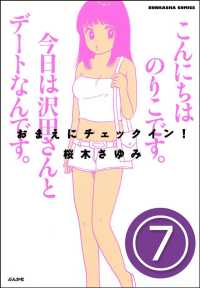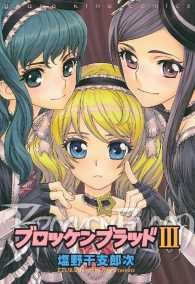内容説明
ミヒャエル・エンデの傑作『モモ』―。人の心を読みとる不思議な力をもった女の子・モモが周囲の人たちに影響を与えてつくる新鮮な世界、そして、“時間どろぼう”と対決して撃退する痛快な物語。世界30数ヵ国に訳されたベストセラーを、シュタイナー教育を底流に見ながら、興味深く解説する。
目次
序章 『モモ』の水面下へ
第1章 人の話を聞く力―新しい聴覚をひらく
第2章 一日の回顧―自己を他者として観察する
第3章 身体・魂・精神―人間の三重性、そして転生
第4章 好奇心と関心―嵐の海の冒険
第5章 魂の領域の登場人物―ベッポとジジと友人たち
第6章 私のなかの灰色の男―テクノロジーの秘密の仕事
第7章 「時間とはいのちなのです」―量で測れない世界
第8章 本質を見抜く力―事実そのものに語らせる
第9章 「ほかの力」の助け―やってきた使者、カシオペイア
第10章 時空の境界線を越える―マイスター・ホラとは何者か
第11章 いのちを送るみなもと―時間を逆にたどる
第12章 「時間の花」―見える音楽、宇宙の言葉
第13章 帰ってきた世界で―認識が力となる
第14章 モラーリッシュ・ファンタジー―直観と決断
第15章 意識の変革―愛し、信じ、希望しつつ