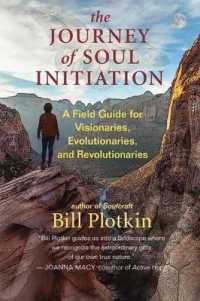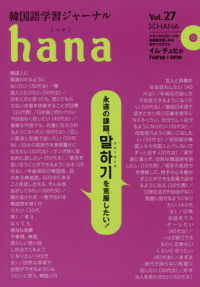内容説明
出羽と飛騨へ、人と風土と伝統に触れる歴史紀行。
目次
秋田県散歩(東北の一印象;象潟へ;占守島;合歓の花;一茶;覚林;植民地?;菅江真澄のこと;旧奈良家住宅;寒風山の下;海辺の森;鹿角へ;狩野亨吉;昌益と亨吉;ふるさとの家;湖南の奇跡;蒼龍窟)
飛騨紀行(飛騨のたくみ;飛騨境橋;春慶塗;左甚五郎;山頂の本丸;三人の人物;国府の赤かぶ;古都・飛騨古川;金銀のわく話;飛騨礼讃)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
84
(秋田県散歩のみ読了)秋田は私の故郷。土地勘はあったが、さすが司馬先生の人と歴史に関する切り口。知らなかったこと多し。「象潟や雨に西施が合歓の花」まずは空港から戦友が住職を務める象潟蚶満寺へ。芭蕉が訪れた頃は鳥海山の山体崩壊により吹き飛ばされた溶岩が湾内に点在、九十九島と呼ばれてた景勝地。後の地震で隆起陸化、今は水田の中に島々。戊辰戦争において奥羽列藩同盟に残り佐幕を貫いた南部藩と早々に薩長方についた秋田藩。両者は戦火を交える。廃藩置県で旧南部領の鹿角郡は秋田県に。その鹿角郡毛馬内に生まれた内藤湖南。⇒ 2023/09/18
キムチ
22
毎回楽しい文明批評を語ってくれている。風貌を思い起し、須田氏のそれと併せ「語りは散弾銃の如く凄まじい」のに、大半がすとんと気持ちにストライク。 氏の東北好きは 私が生まれであるだけに酷く こそばゆく嬉しい。仙台は「東京を向いており」ピュァ東北は岩手だそうな・・なるほど。井上氏に代表されるキャラが「人間の蒸留水で作ったような」という喩がさっくりする。 秋田の風景が楽しい。米作は「宗教」だった。そしてこの風景は江戸の広重の時代に来るべきだ・・うなづける。 飛騨の地は好きで結構探訪しているだけに、気分が高揚2014/01/11
aponchan
19
司馬遼太郎氏の作品乱読中のうちの一冊として読了。高山の町は昔に行った際のことを思い出しながら読んだが、飛騨地方の歴史的背景が分ってから行くとまた見え方が違うと思うので、機会があれば行ってみたいと思わせてくれた。氏の紀行文は、事前の下調べをしたうえで訪ねているので、通常の旅行ガイドとは違い着眼点が面白く、読んでいて飽きない。引き続き氏の作品は読んでいきたいと思う。2020/05/24
クラムボン
15
「秋田県散歩」は日本海に沿って象潟、秋田、八郎潟、能代と北上して内陸の大館と鹿角に至る。紀行文と言うよりは秋田人物誌…それもあまり馴染みの無い人物が多いので気を入れて読んだ。対して「飛騨紀行」は益田(飛騨)川に沿って中山七里、下呂温泉、高山、古川、金銀鉱山で栄えた茂住を辿る。こちらは気軽に読めた。岐阜県の北半分を占める飛騨は五万石足らずだが、領国支配は穏やかで室町期の公卿姉小路氏に始まり、戦国期の京極氏、江戸前期の金森氏から後期の代官支配までゆったり。唯一京極氏の代官三木自綱(これつな)だけが食わせ者だ。2024/08/23
ランラン
8
今年高山へ行ってきましたが、外国人観光客(中国人)の多さに驚きました。街並みを見る限り雰囲気は小京都と言われるように高山の魅力を感じました。高山に高い文化が始まるのは、国主になった金森長近、河重からで、金森家が持っている茶道美学があったからとのこと。「飛騨の匠」を感じられる民家や春慶塗などもう一度言った時には堪能したいと考えています。2015/09/23