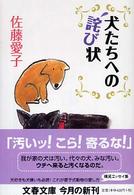内容説明
B29の爆撃で空高く広がる赤い煙。背の高い金髪GIが投げてよこしたガムとチョコレート―。敗戦を境に、5歳の少年が見た日常風景の逆転は、あれから四十余年を経た今も、大きなこだわりとして著者の地肌に染みついている。8・15をはさんで、軍国日本はどう変わったか?自身のこだわりを土台に捉えつつ、戦後民主主義の目で敗戦前後を深く検証する。
目次
ひとつの言葉、ふたつの意思―最高戦争指導会議
戦いの内容はどういうものだったか―特攻隊と沖縄戦
「血の1滴まで戦え」の欺瞞―本土決戦
日本国への無条件降伏勧告―ポツダム宣言
「ヒロシマからナガサキ」までの75時間―原子爆弾
無責任体系のからくり―大本営発表
はたして誰が泣いたのだろうか―8月15日
1億総ザンゲというカタルシス―東久邇内閣
ミズーリ号に翻った星条旗―占領政治
終わりと始まりの儀式―天皇とマッカーサーの会見
戦争の責任はどうとられたか―戦時指導者
解体への序奏曲第一小節―戦後民主主義
庶民は何を見てしまったのか―戦争の総決算
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kamakama
2
かなり前に購入したまま埃をかぶっていた本だった。新版が出ているのを知らなかったが、これは長く読み継がれていかなければいけない本だと思う。 今や当時戦った人たちは90代を超えた。記憶はどんどん風化していく。 残念ながら、敗戦当時の無責任体制は今も抜きがたく、我が国に存在する。 読んでいて怒りを感じる所が各所にあったけれども、この怒りは今の自分自身にも向けていかなければいけないものなのだと、最後の方になってやっと気がつく事ができた。負の歴史の継承はなんとしても避けなければいけない。2014/09/03
unterwelt
0
古本屋で買ったため新版が出ていることは知らなかった。敗戦前後の政府や軍人、一般人がどのように考え、動いていたかを記述しているが、責任の所在が不明になっているところや精神主義が幅を利かせているところは今と変わらないのではという気がしてくる。しかし、本土決戦になったら一般人に竹槍や単発銃で迎え撃たせようとしていた日本軍には呆然とさせられる。アメリカ兵の背後に回って奇襲をかけて殺せ、って忍者ではあるまいし。2016/09/14