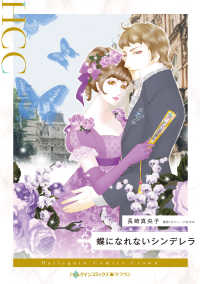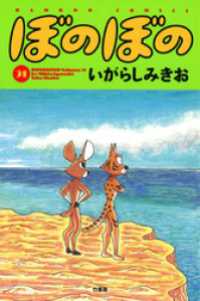感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さつき
61
この巻は新潟、兵庫、高野山、長野と、いろんな地方が舞台になっていました。どの地域も私にとって興味深い土地だったので読みやすかったです。特にブラタモリで観たばかりだった『高野山みち』は数十年前の様子がわかり味わい深かったです。この紀行は高度経済成長期に書かれたせいか、その当時に建てられた新しいビルや、商業的な店に対しての視線がかなり冷たいですね。そんな所も時代を感じて面白いです。2017/09/19
kawa
45
今月の読書旅は、潟(新潟)、播州揖斐川・室津、高野山、信州佐久平。訪ねたい地は室津、九度山真田庵・慈尊院、別所常楽寺・海野宿・信濃国分寺跡など。以前に訪ね豪農ぶりが印象的だった新潟・北方文化博物館(豪農の館)、その規模拡大原因に明治6年・地租改正(金納制に窮した小地主が大地主のもとへ駆け込み的に小作化)にあったとは初知り。かつて、上田にあった信濃国府が我が家近く(松本)に移転した原因、木曽路開墾(713年・「続日本紀」のくだり/284頁)で都との行き来が便利になったためも、身近な蘊蓄でイタダキ。2020/02/16
koji
22
ブラタモリの高野山に触発され読みました。司馬先生とHさんのパチンコ屋論争やら、通りかかった若い僧侶とすれ違った「若者恐怖症」の須田画伯がカバンをすすりあげて身構えた描写やら、クスッと笑える記述もあり楽しんで読めました。それにしても司馬さんの目の付け所には驚かされます。九度山に配流された真田昌幸に志を捨てきれなかった可笑しみを感じたり、丹生官省符神社に高野山の農民搾取の姿を見て取ったり、水原堯栄師のモリアオガエルと真言立川流を結びつけたり、鎌倉期の高野聖重源をおもしろい思想家と言ったり、深みのある歴史観です2017/09/30
なつきネコ@着物ネコ
17
亀田郷の米作りの過酷さは、日本社会の米中心の歴史感を厳しさを知った。司馬さんの不動産批判は的を得ている。不動産の考えはバブルにいたり、経済衰退を招いていた。司馬さんの未来への憂いが、よく見える。播州、高野山、信州と、寺とは違う仏教と関わった人達が見えて面白い。門徒がいたから、毛利は織田とぶつからなければいけなかった。聖が散り、空海の伝承を作り乗っかった。九度山と信州は真田関係の場所だが、昌幸の六紋銭や滋野という、名家の威光を使い昌幸は成り上がり、徳川を相手にした。日本史の裏側の人々の話だった気がする。2017/03/17
TCD NOK
14
観光地でもない、地方都市の更にその中の集落レベルにスポットをあてた紀行ながら、よく読者を飽きさせないなあとつくづく思う。しかし、日本中どんな小さな町村でも歴史があり、教科書に載るような出来事に少なからず因果関係がある。有名な史跡名勝をダイレクトに訪ねるより、そこから二回り三回りぐらい外れたところを紹介しているところが、斜に構えた好奇心を持つマニアにはたまらないんだろう。 あと、今はスマホの地図アプリを開きながら読めるのでより分かりやすい。2019/06/08