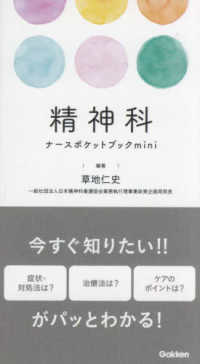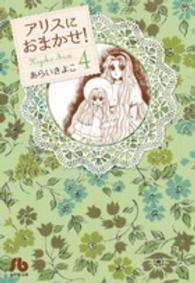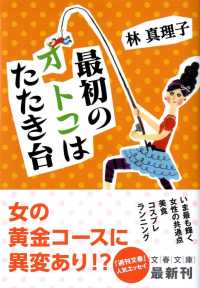内容説明
あるときは辺境に、あるときは東アジアの中心に日本と朝鮮双方で育まれた聖域=アジールの島。中世から近世へ、国家に繰り込まれる対馬を通してみる日本史の縮図。歴史学の気鋭が読み解く絵地図・景観・祝祭。辺境の島から読む新たな日本史。
目次
ソト―“内”と“外”のあわいに立つ島嶼
1部フロンティア―環シナ海世界のなかの「卒土浜」(対馬は円かった!?;古地図のなかの「対馬」;「卒土浜」の誕生)
2部 レッドライス―天道祭から赤米神事へ(赤米の村;中世豆酘の光と影;天道信仰の変容;村の景観;穀霊の神迎え)
3部 アジール―国境の浜、聖域の山(アジール;聖域;卒土;山入;開発;国境;最後のアジール)
著者等紹介
黒田智[クロダサトシ]
1970年埼玉県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。日本学術振興会特別研究員を経て、早稲田大学高等研究所助教。博士(文学)。専門は日本中世文化史。2008年に鹿島美術財団賞優秀者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鯖
20
ゴーストオブツシマプレイ中につき手に取った本。赤米神事等の民俗からみる焼き畑から水田への耕作の移り変わり、朝鮮の側からも日本の側からも虚構の楽園であるアジールとして捉えられていたという側面等について論じた本。表紙となっている朝鮮で描かれた丸っこい対馬の地図と大陸側から見た南北がひっくり返った、太平洋への出口が弓形の日本によって塞がれている地図が印象的。麒麟を見ててもそうなんだけど、網野先生の本をひっさしぶりに読み返したくなった。2020/12/06
kokada_jnet
6
結末の章で描かれる、網野善彦が詳しい調査もないまま「幻視」した対馬のアジール。2009/12/04
竜王五代の人
4
対馬を題材とする三つの論考(古地図に描かれた形状・「伝統ある」儀式の変遷・「卒土」アジール)を収めた本。円くというかクロワッサン形に対馬を描いたのは朝鮮側だけで、境とは言いながら、シームレスに切り替わるのではない。これは地図が日朝両者の中心から見ているせいだろう。ソトも天道も朝鮮由来でありそうで別物になっているところに国境を感じる。2023/09/23
わ!
4
古地図マニアとしては、気になるタイトルなのだが、いざ読んでみると、タイトル部分の謎ときは、マニアからすると当たり前なので、少し残念。ただ全体としては面白かった。この「面白さ」も少し説明が必要で、神社マニアならば楽しめると思える。まずは対馬の信仰対象のうつりかわりと、その推移が細かく説明されているところ…、この様な信仰の祭神の変化は、本土の神社郡にもみられるが、あまり気にとめられることがない。また対馬の豆酘(つつ)という場所を詳しく説明してくれているのが嬉しかった。ここは住吉信仰と関係があるかもしれない所。2023/09/06
Teo
4
タイトルに釣られた。中身はこってり対馬民俗史。タイトルのつもりで読み始めたせいでお腹一杯。タイトルどおりを期待したいなら最初と最後の章で充分と思われる。ただ、折角1,200円も出すのだから中身を充分賞味する方がいいと思う。赤米、稲作、そう言う面での知見は新鮮だった。2009/11/11