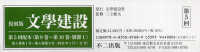出版社内容情報
古代から日本復帰直後までの沖縄の歴史を,青少年向けにわかりやすく,独自の視点から説き明かした幻の名著.
内容説明
米軍占領下の沖縄で、圧政への抵抗運動に理論・実践の両面で献身した著者が、沖縄の日本復帰直後の時期に、若い世代に向けて「これだけは語り伝えておきたい」とやさしく説き明かした、鮮烈な沖縄通史。「島ぐるみ闘争」の歴史の探究が進む中で再び注目の集まる幻の名著。
目次
1 けわしい戦争の雲ゆき
2 沖縄戦の悲劇
3 古代の沖縄と琉球国の成立
4 江戸時代の琉球
5 明治時代の琉球
6 大正・昭和前期の沖縄
7 アメリカ軍政下の沖縄
著者等紹介
国場幸太郎[コクバコウタロウ]
1927‐2008年。那覇市生まれ。1953年、東京大学経済学部を卒業し、米軍統治下の沖縄に帰郷。沖縄人民党に入党し瀬長亀次郎書記長を支えるとともに、地下組織の日本共産党沖縄県委員会書記もつとめ、米軍の武力土地接収に対する農民の抵抗運動(「島ぐるみの土地闘争」)を支援した。後に人民党内の路線対立により沖縄を去り東京に移住、現代沖縄研究に取り組む。1964年より宮崎県で高校・高専の教員をつとめた
新川明[アラカワアキラ]
1931年沖縄生まれ。詩人、ジャーナリスト。沖縄タイムス社編集局長・社長・会長を歴任
鹿野政直[カノマサナオ]
1931年大阪府生まれ。日本近現代史、思想史。早稲田大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あきあかね
22
本書は沖縄の通史を平易な言葉でまとめている。全体の構成で特徴的なのは、沖縄戦から話が始まることと、アメリカ軍政下の記述の分量が多いことだ。 壕で泣いている赤ん坊が、アメリカ軍に気づかれてしまうという理由で日本兵に絞め殺された話をはじめ、凄惨な沖縄戦の模様が克明に描かれる。日本軍は沖縄の人びとを守るためではなく、本土決戦を少しでも引き延ばすために、住民の犠牲を省みない戦いを沖縄で行った。今年の3月に那覇に行った時、少し足を伸ばして慶良間諸島に行ったが、こののどかで澄んだ海に囲まれた楽園のような場所で⇒2022/04/18
二人娘の父
7
非常に興味深い経歴をもつ「国場幸太郎」という人物の描く琉球・沖縄の歴史。人民党から離れた経緯などの詳細を、さらに知りたくなる。いわば沖縄戦後史における革新側からの視点ではあるが、独自の視点とも言える貴重な著作である。ちなみに著者は現職自民党衆院議員・國場幸之助の祖父で、國場組創設者と同姓同名である。混同しがちだが、まったく違う立場の人物でもある。2023/12/09
のん@絵本童話専門
2
ようやく読み終わった!沖縄単体の歴史は知ってるようで知らなかった。私の世代ではもはや分からない沖縄差別。日本からもアメリカからも植民地の扱いを受けていたとは。沖縄の貧困の本も先月読んだところだが、この長年の歴史が経済にも繋がっていると感じた。琉球処分〜日清戦争、太平洋戦争、ベトナム戦争と優しく受け身ゆえ、列強国の大きな歴史の渦に巻き込まれてしまった沖縄。うっすらと残る歴史の知識が繋がっていく知的な面白さを感じられた。詳しい歴史の経緯は何回も読まないと覚えられないが、文章は平易でとても読みやすい!2023/08/31
xncshizu
2
占領米軍に反抗した瀬長亀次郎の同士である国場氏の本。沖縄県のある南洋諸島に人が住み始めた頃から、按司(豪族?)が各地に現れた時代、中国明から始まる朝貢貿易時代、そして島津氏・明治日本・米軍占領時代をたどる。島津氏以降重税を課され、明治政府には選挙・自治を遅らされ、米軍には土地を奪われる。権力者からひどい仕打ちを繰り返される有様には、人々は公正であろうとするものだという私自身の信念が崩されてしまった。「日本はひとつだ」という感覚も怪しいものになってしまった。記憶し、これからの行いに反映させねばならない。2019/10/22
タイガーとらじろう
1
500年ほど前に遡ってまさに沖縄の歩みを、沖縄からの視点、日本からの視点、アメリカからの視点、清からの視点、薩摩からの視点など多岐にわたる視点から描く。筆者は沖縄を「植民地」としての立場を浮き彫りにするがそのように捉えると特にアメリカの行動はわかりやすいし、かつ残酷さがにじみ出る。2025/04/03
-

- 和書
- 水平運動の歴史 (新版)