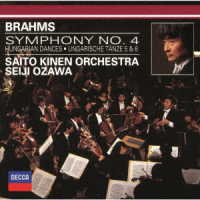内容説明
日本人の戦争観はどのように作られ、変化してきたのか。一億総懺悔論や大東亜戦争肯定論など、政治家・知識人の発言から、戦記物や投書に表れた市井の人の声まで、膨大な素材を検証。対外的には最小限の戦争責任を認めつつ、国内では不問にしてきた様をえぐる。教科書をめぐる史観論争など、近年の動きを補う。
目次
第1章 歴史意識と政治―九〇年代における政策転換
第2章 「太平洋戦争史観」の成立―占領期
第3章 認識の発展を阻むもの―占領から講和へ
第4章 ダブル・スタンダードの成立―一九五〇年代
第5章 戦争体験の「風化」―高度成長期
第6章 経済大国化のなかの変容―一九七〇年代
第7章 ダブル・スタンダードの動揺―一九八〇年代
第8章 歴史からの逃避―現在そして将来
著者等紹介
吉田裕[ヨシダユタカ]
1954年、埼玉県生まれ。77年、東京教育大学文学部卒業。日本近現代史専攻。一橋大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。