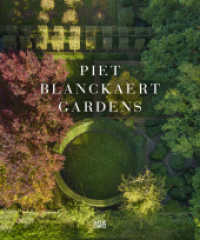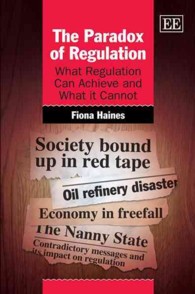内容説明
よい本と出会うことが子どもにとっていかに大切か、よい本を選び出す基準とはどのようなものか。子どもの本の多様なジャンルの特質に即して、よい本の評価基準を詳しく説き明かす本書は、長年にわたり児童文学や児童図書館に関わる人々の厚い信頼を得てきた。日本を代表する三人の児童文学者が訳した名著が文庫版で甦る。
目次
児童文学の問題
児童文学の系譜
批評の態度
昔話
神々と人間
叙事詩とサガの英雄たち
詩
絵本
ストーリー
ファンタジー
歴史小説
知識の本
著者等紹介
スミス,リリアン・H.[スミス,リリアンH.] [Smith,Lillian H.]
1887‐1983年。児童図書館員、児童文学者。カナダとアメリカの児童図書館活動の中心として活躍
石井桃子[イシイモモコ]
1907‐2008年
瀬田貞二[セタテイジ]
1916‐79年
渡辺茂男[ワタナベシゲオ]
1928‐2006年(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鳩羽
13
子どものための本を、「昔話」「神話」「詩」「知識の本」などのカテゴリに分けて、それぞれがどういうもので、子どもに自信を持って勧めるためにはどういった批評眼を持って見るべきかなとを解説する。子どものような素直な気持ちで楽しめるかどうかも大事だが、大人の経験と知性でもって、その本が本当に子どもにとって読む価値のあるのかを冷静に判別することも、大人の役目なのだろう。成長を望み、面白いストーリーから、あるいは本の知識から、世の中を知ろうとする子どもにとって有意なものをという感覚が、大人としての責任を感じさせる。2018/06/05
月音
7
再読。子供は面白がっていても、大人から見ればどうにもお粗末な内容の本というのは、遺憾ながら昔も今も数多くある。浜の真砂のごとくある子供の本の中から金の粒──健やかな成長の糧となる価値ある文学を見出すための評価の基準とは何か。著者は現代の良書を選ぶには、古典作品を評価することがその助けとなると説く。本書はジャンル別に名作とされる諸作をあげ、固有の特質と子供の心にどのように働きかけるかを分析していく。昔話・神話を最初に取り上げているのは、最古の文学だからという以上の考えあってのことと思えた。⇒続2025/09/16
chacha子
6
面白かった。真に子どもが愛する物語を守るということ。児童書に関しては、子どものほうが、審美眼に優れている。2024/01/27
壱
5
圧倒的な知識量の中で溺れながら、辛うじて読み取れるものをひたすらメモした。「はたして自分は、この中の何万分の一でも、“良い読書”というものをしてきただろうか?」と何度も何度も自問。いろんな図書館員の先輩方の選書基準を聞いてみたいと思った。2018/01/09
ローリングエルボー
3
なかなか役に立つ本。児童文学も奥が深い。2018/09/09
-

- 電子書籍
- アラサークエスト(2) ヤングキングコ…