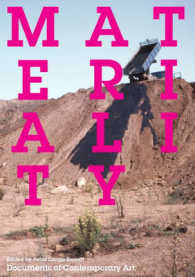内容説明
一葉、啄木、漱石などの「過去」の日本近代文学の古典作品を、「現在」の小説の中に呼び出し、「現在」の小説には、「過去」の古典作品と交流させる。現代の文芸批評を先導する著者が、文学史の陳列棚に並べられた古典作品と現代の最前線の小説を自在に対話させる。小説を読む本当のたのしさを味わうための格好の一冊。
目次
はじめに 『大人にはわからない日本文学史』のできるまで
1日目 「文学史」を樋口一葉で折りたたむとすれば
2日目 「文学史」が綿矢りさを生み出した
3日目 小説の文章が最後にたどり着いた場所
4日目 自然主義をひっぱたきたい
5日目 「日本文学戦争」戦後秘話
6日目 小説のOSを更新する日
7日目 文学史の「晩年」から次の千年の文学へ
著者等紹介
高橋源一郎[タカハシゲンイチロウ]
1951年広島県生まれ。作家。明治学院大学国際学部教授。81年、『さようなら、ギャングたち』で群像新人長編小説優秀賞、88年、『優雅で感傷的な日本野球』で第一回三島由紀夫賞、2002年、『日本文学盛衰史』で伊藤整文学賞、2012年、『さよならクリストファー・ロビン』で谷崎潤一郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
64
歴史や社会構造という規定されたものから完全に自由になった小説というものを読んでみたいけれど、おそらく無理(書くのはもっと無理)なのだろう。講演の動画を観たら高橋先生ご自身も小説の背景にある時代を意識して読め、的なことをおっしゃっていた。うむむ、でもそれでも、限界を壊すのがアーティストなのではないのか。ふわっとした感想しか持てない自分がどうにももどかしい。2018/04/07
ちぇけら
26
高橋源一郎は言う。綿矢りさを読むと樋口一葉や国木田独歩の『武蔵野』が思い出されると。同時代に書かれた『蒲団』と『道草』よりも、『蒲団』と『恋空』のほうが似ていると。穂村弘の『短歌の友人』で書かれていることは、近代から現代の小説についてでも同じではないかと。小説の世界にいながら、小説についてこれだけ考えられる源一郎さんはめちゃくちゃすごい。小説はこれまでもこれからも、きっと同じようなことを描き続けるのかもしれない。あるいは、「私」が消えた世界で、新たな小説が生まれるのかもしれない。2019/05/19
ころこ
23
普通のひとが見過ごしてしまうものに立ち止まり、大きく驚く、著者の小説はそのようなものを書いてきましたが、本書についても同様の問題意識がうかがえます。2日目にある、綿矢りさ『インストール』が国木田独歩『武蔵野』に触発されて書かれたという事実はないでしょう。むしろ、そのように解釈していくことで、文学史をつくっていく。本書で行われているのは、既に出来合いの文学史を語ることではなく、講演で語ったこととその再構成の仕事のうちにも、「文学」の生成は行われているということです。同じく2日目に、小説と詩の違いとして、小説2018/02/23
koke
12
再読。解説で穂村弘が言うように、現在と過去、小説と詩歌など、互いの外部であるような組み合わせを利用して「リアルタイムの文学史」を可能にしている。なるほど、過去の小説を読むことで現在の小説が読める、現在の小説を読むことで過去の小説が読める、というのが文学史の一番の効用かもしれない。たとえば今「現在しかない」小説が書かれていると言うが、著者は「歴史のある」小説と対照してそれについて考えている。歴史意識のない私にふさわしい小説だが、歴史意識のある小説との対比ではじめてその特徴が際立ってくるわけだ。2024/07/19
りょう
12
高校の時の文学史の授業が素晴らしくつまらなかったので、それ以来文学史に触れることはなかった。まあしかしこの本を読むと、文学史は作者-作品名の暗記なんかではなくて、ちゃんと『歴史』なんだなということを気づかせてくれるわけでして、そして筆者の論がなかなか結構、面白いわけです。でもまあ、このレベルを国語の先生に求めるのは流石に酷か。2014/06/02
-

- 電子書籍
- カフェで何をお探しですか
-

- 電子書籍
- クリスティーヌ中島自選集 (5) 肩幅…