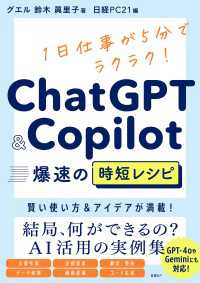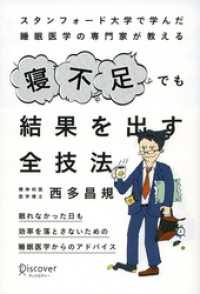出版社内容情報
音読から黙読へ-天保期から戦後大衆社会に至る読者の実態を,出版機構の構造,作者の意識なども含めて歴史的に考察.活字文化の王座がゆらぎはじめ,近代の意味が問い直される時代の文学研究に新局面を拓いた問題作.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
15
江戸後期の出版統制から明治の大変化を経て昭和の文学状況へ。長いスパンに及ぶ読者像の変遷を詳細なデータで分析・批評しており、読み応え抜群。特に、菊池寛の諸作の作品分析と婦人雑誌の受容研究が同時に成される「大正後期通俗小説の展開」は、うねるような文学状況の変化がドラマティックに読み取れてとても刺激的。読者を知ることは作品を知ることに繋がる。それは鴎外や四迷に対する著者の言葉を読めばよくわかる。藝術を考える上での古典、誰が読んでも益がある。本書の精神で今の読者について書くとしたら、どのようなものになるだろう。2016/12/15
わんにゃん
7
大熊の指摘が色々面白かった。「新聞小説の作品内容が、全体として読者自身の生活と並行して発展しつつあるような錯覚がもたらされ」「新聞小説は他のいかなる文学ジャンルにもまして、読者の日常生活、現実的関心に裏づけられた実在感を保証されている文学形式」だったりラジオドラマが「聴取者の側に属してゐるところの想像力といふ一つの大きな人間的能力に依頼し、その能力の喚起と活動とを聴取者に期待する形式である」だったり。2022/01/30
はるたろうQQ
5
前田愛は、瀬戸内寂聴と近代日本文学の名作の地を歩いて対談する本を読んで、その名を知った。もう30年以上前のことか。樋口一葉の本も愛読した。久しぶりにこの大家の高名な作品を読んだ。中でも「大正後期通俗小説の展開」は、国文学者ならではの作品そのものの分析もあって、享受者と創造主体者の相互関係を解明しようとする熱意に溢れ、単なる外在的な読者層分析に止まらない。また言文一致体の本当の意義や意味は「音読から黙読へ」に詳しい。二葉亭四迷「浮雲」を読むとその前半と後半の書き方の違いに驚くが、その謎解きにもなっている。2018/04/24
oz
5
初読。読者論は文学理論における受容理論の中核で、テクストは読者の参加を経て初めて潜在的な可能性が具体化される。日本における読者は活版印刷の普及により大量の活字を消化することへの馴致を経て、素読を始めとする音読文化を滅ぼし個人的な黙読文化を選んだ。現代の読者は可処分時間のごく一部を多様なテクストにランダムアクセスできる移ろいやすい存在で、かつてのように読むべき聖典(カノン)もない。それでも本書の射程内を脱するほどには頽廃していない。2017/08/11
Was
5
名著。江戸末期から昭和期に至るまで、読み聞かせという受容経験を生む場およびジャンル=解釈共同体の消滅と、それ以降の読書形式の細分化をこれでもかというくらい丁寧に追う。取りあげられている菊池寛の『真珠夫人』はメディアミックスの先駆けである。今読んでも得るものはたくさんある筈だ。2013/01/18