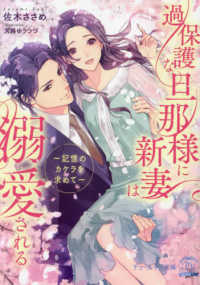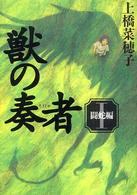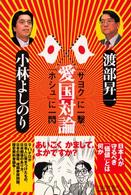出版社内容情報
今やナショナリズム論の古典となった『想像の共同体』の著者、ベネディクト・アンダーソンが自身の研究と人生を振り返り、学問を志す若い読者に向けて綴った本。当時の欧米の学問的制度のあり方や、比較研究・地域研究分野の勃興などにも触れながら、自らの学問的・文化的枠組を超えて自由に生き、学ぶことの大切さを説く。
内容説明
今やナショナリズム論の古典となった『想像の共同体』の著者B・アンダーソンが、自身の人生と研究の軌跡を大きな歴史の流れに位置づけつつ振り返り、日本の若い読者に向けて綴った回想録。欧米の学問的制度の変容、地域研究の誕生と発展、フィールドワークの意味、比較研究の重要性などに触れながら、自らの国や文化、学問的枠組みを越境し、自由に生き・考えることの大切さを説く。
目次
第1章 人生の幸運―幼少期からケンブリッジ大学まで
第2章 個人的体験としての地域研究―東南アジア研究を中心に
第3章 フィールドワークの経験から―インドネシア・シャム・フィリピン
第4章 比較の枠組み
第5章 ディシプリンと学際的研究をめぐって
第6章 新たな始まり
著者等紹介
アンダーソン,ベネディクト[アンダーソン,ベネディクト] [Anderson,Benedict]
1936‐2015年。コーネル大学名誉教授
加藤剛[カトウツヨシ]
1943年生まれ。一橋大学社会学部卒業。コーネル大学でPh.D.(社会学)。京都大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山口透析鉄
PETE
taq
ふら〜
sansdieu