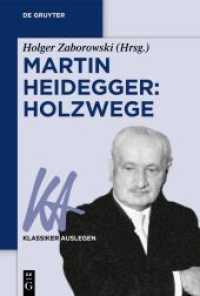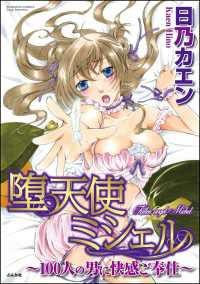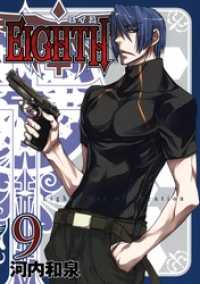出版社内容情報
「共生」という言葉に込められた様々なモチーフを、孤独、ケア、教育、臨床、エコロジーなど様々な場面における問題群から考える。現代社会の抱える諸問題を、主に倫理学の観点から、これまでの議論を紹介しつつ、集中講義形式のやわらかな口調で解説する。巻末に詳細な文献案内を付し、倫理学の教科書としても最適な一冊。
内容説明
「共生」という言葉に込められた様々なモチーフを、孤独、ケア、教育、臨床、エコロジー、人権といった諸局面に即して読み分ける。“共にどう生きるか”という問いを携えて、現代社会が抱える多様な問題に接近し、やわらかな会話体で解説する。巻末に各テーマを掘り下げる手がかりとなる作品を精選したブックガイドを付し、倫理学の教科書としても最適な一冊。
目次
講義の七日間 共に生きる
第1日 「共生」の両義性
第2日 孤独と共生
第3日 ケアと共生
第4日 教育と共生
第5日 臨床と共生
第6日 エコロジーと共生
第7日 「あなたを苦しめているものは何ですか」
補講 人間の権利の再定義―三つの道具を使いこなして
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
呼戯人
19
倫理とか道徳というものは、人類が共生する動物でなければ 必要ないものです。他者と他者の間に、倫理がある。その問題を、孤独、ケア、教育、臨床、エコロジーなどとともに取り上げ論じてゆく倫理学の本。とても読みやすい。わかりやすい。これからの時代、トランプのような人種差別や女性差別やそういったものを肯定してしまう流れとは別に、やはり多文化共生の潮流を推し進めてゆく必要性を感じた本でした。2025/03/25
しんすけ
19
カントは道徳を義務として語っている。 そこには人が義務を護らなけらなければ、社会生活は成り立たないとい強い意志が観えた。 本書では義務を維持して生きるための究極の要素として、道徳が語られているかに観える。 それを具現化した言葉が、タイトル見る「共生」である。 しかし義務をお題目のように唱えていても、だれも義務として捉えることもないだろう。 本書の半ばにはジョン・ロールズへの言及がある。それは自然に制度として進化させたいという希望である。 希望は叶うものではないと考えるのは、腐ったルサンチマンに過ぎない。2023/03/16
ほし
15
「共生」を軸に、ケアや教育、臨床などを講義形式で論じる一冊。共生を単なるユートピア的なものとして扱わず、「生の諸様式の雑然たる賑わい」を求めるコンヴィヴィアリティという概念や、共生の持つ他者への侵犯性や相互依存性、孤独を取り上げながら、他者なしでは生きられない人間にとっての共生のありようが考察されています。本書に引用されている、石原吉郎による「日常生活をていねいに生きよ」、宮沢賢治による「どうか今のご生活を大切にお護り下さい」という文言が心の深くに響きました。この本を起点に、色々と学びたいと思います。2022/12/31
ドラマチックガス
10
講義の形を取りながら「共生」について様々な角度から検討する。一見関係なさそうな話が、その章が終わる頃には共生とは何かを考える題材になっている。一章一章も短くとても読みやすい。ただ、僕が今求めているものではなかった。理念的な物というよりはもう少し具体的、実践的なものを読みたかった。そういった本をたくさん読んで、このテーマへの関心がもっと高まったら、改めて読み直したい。2024/08/24
YT
8
〈共生〉の生物的な使用と思想としての使用に整理し様々なエッセイやケアの倫理、教育・臨床、エコロジー・フェミニズムを通して〈共生〉を考える。倫理学者の著者だが、哲学の外部の議論が多数使われていることから、幅広い視野を提供してくれる。石原吉郎とヴェイユ、ケア周辺の議論をさらに掘り下げていきたい。 本書を貫く〈共生〉の概念に強く答えを与えてくれるわけでもなく、様々なトピックから自分で考えるフックを提供してくれる本だと思う。〈共生〉について問題意識を抱え、考え続ける人達にとってはかなり刺激的な読書になると思う。2025/12/16