内容説明
『学問のすすめ』は、福沢諭吉の第一の主著であり、明治期を代表するベスト・セラーである。当時の日本人の精神形成に計り知れぬ影響を与えた。さらに、戦後から現代まで、近代的・合理主義的な人間観、学問観の出発を示す書として、読み継がれてきた国民的古典である。伊藤正雄による現代語訳は、原文の意味を尊重したわかり易い文体で、内容も把握し易く工夫されている。
目次
人は同等なること(人権平等論)
国は同等なること(国権平等論)
一身独立して一国独立すること(個人の独立即国家の独立)
学者の職分を論ず(民間学者の責任)
明治七年一月一日の詞(日本学徒の覚悟)
国法の貴きを論ず(順法精神の必要)
国民の職分を論ず(義に殉ぜよ)
わが心をもって他人の身を制すべからず(男尊女卑と家父長専制との弊)
学問の旨を二様に記して、中津の旧友に贈る文(少年よ、大志を抱け)
前編の続き、中津の旧友に贈る(外尊内卑を脱却せよ)〔ほか〕
著者等紹介
福沢諭吉[フクザワユキチ]
1835‐1901年。中津藩士、教育者、啓蒙思想家。幕府の遣外使節団として欧州・米国を廻り、多くの西洋紹介書を著した。明治維新後は、慶應義塾の創設・教育と、「時事新報」を創刊して自由主義思想擁護の立場に立った
伊藤正雄[イトウマサオ]
1902‐1978年。東京帝大国文学科卒。甲南大学教授、神戸女子大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
-
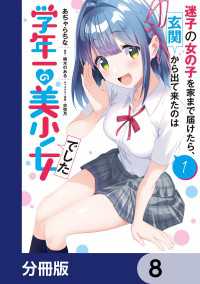
- 電子書籍
- 迷子の女の子を家まで届けたら、玄関から…
-
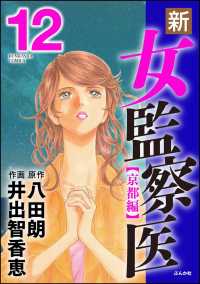
- 電子書籍
- 新・女監察医【京都編】 12






