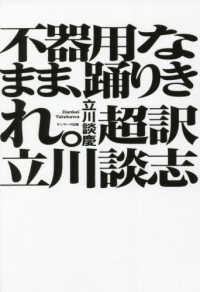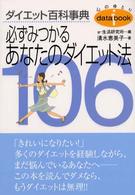出版社内容情報
文化記号論を導きに,政治権力の問題に対する斬新な見方を,多くの具体例に即して提示する.また身体・パフォーマンス・女性・演劇などを手掛かりに,文化の深層に新たな光を照射する.著者の80年代の理論展開の軌跡をたどる.
内容説明
文化記号論を導きにダイナミックな理論を構築する多彩な試み。第2巻では、政治権力の問題に対する斬新な見方を多くの具体例に即して提示する一方、身体・パフォーマンス・女性・演劇などを手掛かりに、文化の深層に新たな光を照射する。
目次
1 根源的パフォーマンス
2 文化のなかの文体
3 スケープゴートの詩学へ
4 女性の記号論的位相―クリステヴァ『中国婦女』をめぐって
5 記号としての裸婦―大江健三郎あるいは裸体の想像力
6 足から見た世界
7 交換と媒介の磁場
8 書物という名の劇場
著者等紹介
山口昌男[ヤマグチマサオ]
1931年北海道生まれ。55年東京大学文学部国史学科卒業後、東京都立大学大学院で文化人類学を専攻。東京外国語大学教授、静岡県立大学教授を経て、現在札幌大学学長。「中心と周縁」「スケープゴート」「道化」などの概念を駆使して独自の文化理論を展開している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





読書という航海の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
8
「現地調査抜きのために、人類学的素材を扱いながら否定の対象となったという点では、フロイト、エリアーデ、そして今日『暴力と聖なるもの』によってスケープゴート理論のもっとも精力的な推進者であるルネ・ジラールも含まれるーということ自体、まことに奇異な光景と言わざるを得ない…一方、『汚穢と禁忌』において、一種のスケープゴート理論をこの用語を使わずに展開したM・ダグラスは大歓迎されている。ダグラスは現地調査によるモノグラフという免罪符を入手してからこの理論を展開し、フレーザーの『金枝篇』の新版の序文すら書いている」2019/05/29
四四三屋
1
本書は著者の中心的課題である『スケープゴート』『中心と周縁』というテーマについては一貫しているように思えます。それなのに何か統一感がかけているような印象を受けました。そうした印象が奈辺から生じるのか、それを考えるのが本書の読みどころなのかも知れません。2014/04/05
mstr_kk
1
圧倒的博覧強記。このくらいまとめて読むと、字面の裏から、理論には収まらない「垂直的」な迫力が伝わってくる。僕の個人的な関心からすると、「交換と媒介の磁場」が、2巻通じてのハイライトだと思う。小説、テレビ、演劇にまたがる物語論の、現在のところの決定版ではないだろうか。2013/03/13
-

- 和書
- まど・みちお詩と童謡